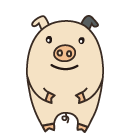小さな国語塾のつぶやき
柑橘類
シトラス系(柑橘類)の香りが一番人気!だとテレビ番組の調査で、先日見たことがある。真剣に見てたわけではないので、アンケート対象などはよく分からないが・・・。確かに、柑橘系の香りは甘酸っぱくてしかもスーッとするので快適な気分になりリフレッシュ効果があると科学的にも実証されている。さて、昨日は熊本の友人から大量の蜜柑が送られてきた。「冬はやはり蜜柑」とばかりに香りのみならず味も楽しみながら、ふと先のアンケート結果や、昔の有名な小説を思い出した。リラックス効果などが科学的に実証される云々に限らず、経験的に?!人間は知っていたに違いない。柑橘系の果物を題材にした有名な小説がある。芥川龍之介の「蜜柑」、梶井基次郎の「檸檬」である。共に書き出しは暗い雰囲気だったのだが、蜜柑やレモンの登場から場面が徐々に変わっていく・・・・。短い小説でネットでも読めると思うのでぜひおすすめである。
2015/11/28 17:37
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
外来語
今週から後期中間テストが帯広で、来週からは芽室で始まる。それに伴い、今週と来週は国語塾ではテスト対策をしている。中学3年生では、外来語、漢語、和語、和語+外来語などなどを学習しており懐かしい気分で見ていた。が、当然、当事者の生徒はそんな悠長なことを言ってられるわけもなく皆必死で取り組んでいた。そのなかで「たばこ」という設問があり、全員「和語」と書いて×。答えは「外来語」。平仮名だったため全く躊躇せずに「和語」と選んだ彼ら、それは当然だろう。なぜなら「たばこ」は英語では「シガレット」だし・・・でも解答には無情にも「和語」としか記されておらず「????」の表情。実は、「たばこ」はポルトガル語が語源だと説明してようやく彼らは納得。ちなみにポルトガル語が語源の言葉は「こんぺいとう」「かすてら」「かぼちゃ」などなど意外と多い。解答しか書かれておらず納得がいかない時は、知っている人に聞く、あるいは今はパソコンやスマホという便利な道具があるので、それらを使って調べるなどしてきちんと理解して覚えるとテスト対策になることはもちろん、教養として今後役立つので面倒がらずに疑問をきちんと解消してほしいと願った一コマであった。
2015/11/27 13:56
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
出会い
昨日、友人から沢山のお団子をいただいた。何種類もいただき、そのどれもが本当に美味しくて美味しくて!幸せだなあとしみじみと味わいながら食べたのだが・・・。ふと「なんで団子、団+子なんだろう?」と疑問に思い調べてみた。遣唐使が持ち帰ったお菓子の一つである「団喜」が粉を使うことから「団粉」になり、それが「団子」に変化したという説が有力らしい。成程~と思った時にふと、「扇子(せんす)は扇の子」と書き「団扇(うちわ)」は「団+扇」・・・・と「団」と「子」を使う熟語がどんどんと頭の中に広がってきた。そもそも扇子と団扇の違いは?などなど。扇子と団扇の違いについては先ほど調べてみたのだが、字数および時間的にここに記すのは無理なので気になる方はぜひご自分で。さて、今日は午前中にある物事を電話で専門家に相談し、午後からは国語塾について知りたい方の訪問を受けた。国語塾のことからどんどん話が脱線し…楽しい時間を過ごさせてもらったのだが、不思議なことに自分が午前中に専門家に相談したことを全く同じ内容、考えを、今日おみえになった方の口から出てきたことにはただただビックリ。不思議なことがあるんだなあと興奮気味。国語塾を開講しているおかげでこうしてブログを書けること、ちょっとした日常に疑問を持つようになったこと、様々な出会いや出来事に巡り会えることに対して感謝!
2015/11/26 20:48
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
猫ブーム
最近、空前の猫ブームだとか。今朝のテレビ番組でも特集が組まれていたり、帯広でも9月から11月23日まで「猫まみれ展」が開催されていた。なぜ、今「猫」なのか?人気の理由は「飼いやすさ」!散歩もしつけもいらないし癒される、犬ほどには鳴き声で周囲に迷惑をかけることが少ない等があげられる。時代が変わると猫に対する見方がこんなにも変わるのかと不思議な気分。昔話や宮沢賢治作の「注文の多い料理店」では化け猫が登場し、昔は猫はミステリアスといった位置づけだったが。ネコが妖怪視されたのは、ネコは夜行性で眼が光り、時刻によって瞳の形が変わる、足音を立てずに歩く、爪の鋭さ、身軽さや敏捷性といった性質からだと考えられている。ある一つの物事を敵対視するのもよくないが、逆に良い面だけをピックアップするのもどうか。先に、猫の人気は「飼いやすさ」と書いたが、それは何と比べてなのか?をはっきりさせないといけない。生き物を飼うということは命を預かること、安易に「飼いやすさ」という言葉や良い面だけを見るのは避けたいもの。そういった冷静な視点や論理的思考を養うためにも、日々頑張って国語力をきちんと身につける必要があるとひしひしと感じる今日この頃。
2015/11/25 16:09
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
勤労感謝の日
昨日は「勤労感謝の日」で祝日。字からして「勤労している人に感謝する日」だと思っている人が多いのでは?かくいう自分自身も長年そう思っていた。それに対して作家の猪瀬直樹氏は次のように述べている。「『勤労感謝の日』が新嘗祭であることを知らない人が多い。戦後にGHQの指示で意味不明の変な名前にされた。収穫祭ですよ。稲穂が垂れ、風に揺れる光景にほっとするのは、食糧が確保されたという根源的な安心感に浸されるからです。皇居で天皇がカミに祈る儀式が行われる。」そう、もともとは収穫に感謝する「新嘗祭」が行われていた日だが、戦後の改革で「勤労感謝の日」となった。そういった由来を知らない人が多いこと、「GHQに変な名前にされた」と猪瀬氏は憤っているが・・・。様々な日本語の意味は変化する、また戦前の日本は農業を営む人(一次産業従事の人)が多かっただろうが今は様々な職業の人が多く、第三次産業従事者(サービス業など)が増えている。つまり「新嘗祭」から「勤労感謝の日」と名前が戦後に変わるとともに本来の意味を知る人が少なく、意味が変わりつつあるが、そのことを憤るよりも言葉通りに働く人、さらには働くことによって得られた収穫されたものなどなどに感謝をすることが大切なのでは?とぼんやりと考えた一日であった。
2015/11/24 19:21
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
一生の財産
本年度の読書感想文の審査が始まった。複数の審査員で輪番で期間を決めて読んでいくことになり、今年はトップバッターで多数の感想文を預かった。張り切って、読み始めたところ・・・①書き出しを一文字下げていない②段落がなく、エンドレスに書いている③誤字という3点があまりにも多く、愕然としている。③に関してはまあ、仕方がないかという気がしなくもないが、①と②に関してはかなりのショックである。ちなみ今年も中学3年生を担当させてもらっている。つまり、中学3年生がこの状態ということは他の下の学年は・・・・と思うと暗澹たる気持ちになる。テストで「50字以内で書け」といった記述では、一マスあけずに書き始めるし、日ごろ原稿用紙に文章を書くという経験が少ないからという背景があることも重々承知だが、それでも彼らに声を大にしていいたい。早ければ3、4年後には社会に出るわけであって、その時にきちんとした形式の文章を書けることを当然要求される。大学や専門学校に進学するにあたってもレポートや試験で文章を書くことになる。「きちんとした文章を書ける」ことは一生の財産!年に一度の感想文、取りあえずこなしておけばいい…と思わず「将来のため」と少し視点を変えて取り組んでほしいものだ。
2015/11/24 19:21
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
本の紹介
最近、「5分後に意外な結末」(学研教育出版)というシリーズが話題をよんでいる。ショートショートの話が20話ほど収められており、シリーズで数冊出ている。①一話が短いので、どこからでも読める②オチがあり、起承転結がはっきりしている③落語、西洋の小噺、現代の創作などが収録されており偏っていない、この3点がお勧めの理由。授業でも何らかの方法で使えないかなあと、とりあえず3冊購入し、すっかりはまっている。(※自分がはまるだけでなく、試験的に授業でも使用中)。ショートショートと言えば、星新一氏が大御所だが今の小中学生にはあまりなじみがないかもしれない。先の「5分後・・・」シリーズの方が平易、字が大きい、イラストや装丁が工夫されているのでとっつきやすい。というわけで「5分後・・・」シリーズで読書の楽しみを味わった生徒には、ぜひぜひ星新一のショートショートを勧めてみようとひそかに企んでいる。
2015/11/23 12:10
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
スモールステップ
どの科目でもそうだが、いわゆる「解き方」を教えてもなかなかその通りにはできない。たとえば「言い換え」部分にはすべてチェックすると説明し、少しの見本を見せただけでは、まず自力ではできない。ましてや三十字、四十字・・・といった記述はいきなりは書けない。配った資料を見たり、説明を聞きながらなんとか書いたとしても解答を見ると自分が書いたものが正解かどうかは判断できないことがほとんど。ではどうするか?慌てず段階を追って進めていく、つまりスモールステップが大切。そんなわけで授業ではあの手この手と品を変えて、同じ内容の練習をすることにしている。時間はかかるが、必ず出来るようになると信じつつ。初めて字を覚える時だって何回も何回も練習してたはずだが、小さい頃のことなのであまり記憶にないかもしれない。が、よく見かける光景としては補助なし自転車の練習。片方ずつペダルを外してみたり、はたまた保護者が後ろを支えつつ時々手を放したり・・・最近では転ばないでも乗れるようになる「ストライダー」なんていう乗り物もある。成程、ストライダーでバランス練習をしてからペダル付きの補助輪なしの自転車にステップアップすると無理なくスムーズに移行できるだろう。何事もスモールステップが一番の近道。
2015/11/21 03:39
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
大熊猫
「大熊猫」と書いて何と読むか?答えは「パンダ」。お恥ずかしいながら、これは昨夜、生徒からのクイズだったのだが、答えられず教えてもらった。さて「熊」というのはなんとなく分かるのだが、なぜ「猫?」と思った人が多いのではないだろうか?当時の中国では、一般の人は、右から左に文字を書く。ところが、中国の生物学界では既に西欧流に左から右に文字を書く方法を採用していたという。そして、パンダの標本には「猫熊」という表示がつけられていたが、パンダを見に来た一般の人たちは、これを「熊猫」と読んでしまい、以来、誤った呼称である 「熊猫」 が一般化したそうだ。(『西南師範大学 漢語言文字学研究叢書第二輯 漢語動物命名考釈』 )つまり「大熊猫」 は、本来は「大猫熊」 だったという。それならば、何となく納得。何事も丸覚えしようと思ってもなかなか難しいが、理由や由来が分かり納得するとストンと腑に落ちる。漢字はもとより、古語が現代語と同じ単語ながら意味が違う場合が多いが、それについては極力由来などを説明するように心がけている、少しでも納得することによって記憶に残ってほしいと願いながら。さて、今から今日の授業の準備をするとしよう。
2015/11/20 12:58
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
短所を長所に
空中で体を反転させるスゴ技の秘密を科学者が解き明かした・・・コウモリがどうやってこの技を成功させているのかは、長い間謎とされてきた。飛ぶ生物の中でも、彼らはその体重の割に非常に重たい翼を持っているからだ。科学者たちはようやくその答えをつかんだようだ。コウモリは厄介な翼を長所に変え、その重さを利用することで、上下逆さまになる際に必要な力を得ているのだという。(ヤフーニュースより)これを読んで、自分が中学時代の恩師の言葉を思い出した。中学校の美術担当、N先生は「僕は美術が苦手だったから美術の先生になった」とおっしゃったが、今となっては成程と納得。自分の苦手意識という短所を長所に変えることによって(むろん、たゆまぬ努力で苦手意識を克服されたという前提があるが)生徒の気持ちや教えるべきツボが分かる素晴らしい指導者になりうる。かくいう自分自身も人様の評価はともかくとして、自分の中では書くことが苦手で、かなりの時間を要していた。だからこそ、まずは「型」を学び・・・・と素直になれた部分がある。苦手を苦手のままとするか、苦手という短所を長所に生かすかは本人の意識次第か。
2015/11/19 14:06
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です