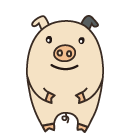小さな国語塾のつぶやき
時代変化
毎年のことだが、この時期になると一年間を振り返り反省、来年度の目標を立てている。さらには・・・世の中が明らかに変わっていることを実感。例えば激安のバーガーよりも高くても安全なバーガーが躍進する、列車業界では通勤ラッシュ時に必ず座れる列車を導入(前もって整理券を当日に購入)などなど。要するに①ニーズが多様化している②高くても「質、満足感、時間」を買うという人が増えつつある・・・おかげで、少子化のこのご時世、芽室の住宅街で国語しか教えない、コマ数も少ない、一コマ限定4名までという制約が多い国語教室だが、おかげで遠方からの問い合わせが増えつつある。ちなみに国語においても、先日からちょくちょくと書いているが①明らかに記述問題が増えつつある②一つの作品を長時間かけてじっくりと考えるよりも割とサラッと授業が進むなど。それが良いかどうかは別として、明らかに変化しつつ流れをキチンと把握し、対応することが大切であり、そうすることが自分の目標を達成する近道になる。
2015/12/08 13:36
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
「不言実行」「有言実行」
「不言実行(あれこれ言わず、黙ってなすべきことを実行すること)」「有言実行(口にしたことは、何が何でも成し遂げるということ)」という四字熟語がある。一文字違うだけで漢字の構造などよく似ていると気づいた人も多いのでは?それは当然のことで、そもそもが「有言実行」という言葉は「不言実行」をもじって作られた言葉。さて、昔は前者の「不言実行」が日本人気質に合っており、よしとされていたが、最近は宣言したことを何としてもやり抜くことが美徳とされつつある。個人的には・・・その場その場で使い分けすればよく、どちらがいい悪いはないと思っている。ただ、自分自身の性格を考えると「有言実行」が良い意味でプレッシャーになって頑張れるので基本的には「有言実行」派か。さて、最近はどこでもクリスマス一色!お店に行くとクリスマスソング、オーナメント、ラジオをつければ、やはりクリスマスソングやクリスマスの話題。クリスマスソングが流れてくると、一緒になってハモル・・・・わけではなく、思わず歌詞を古文に翻訳したらどうなるか?と真剣に考えている今日この頃。かなりの職業病というべきか?単なる変わり者というべきか。どちらにしてもクリスマスまでに、誰もが知っており、しかも訳しやすいクリスマスソングを古文バージョンに翻訳しようと決め、ここで宣言する!講ご期待?!
2015/12/07 13:00
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
記述に伴う要約
最近の傾向として、中学国語のテストでは記述問題が明らかに増えており、それらは中学生にとって一番苦手とする分野。逆に言うと記述を克服すれば国語という教科が点数源となって全科目の総合点の底上げとなるので、なんとか頑張って踏ん張ってほしいところ。さて、複数の指定された言葉を使って記述する場合は指定された言葉を本文でチェック、それらを要約すればいいわけだが・・・。例えば3文を要約するとなると、どうしても慣れないうちはとりあえず、それぞれの文章から一部抜粋してその抜粋した部分を無理やりくっつける。そのため文章として意味が通じなくなることがしばしば。コツとしては必要な個所をピックアップしたら、それらをパズルのように並べ替えて一番ピッタリくる順番にして文章にすること。例えば、目の前にキャップ付きのペンが3本あったとする(赤、黄色、紫)。それらを本体とキャップをバラバラにして組み替えて3本を2本にするといったイメージか(赤の本体に黄色のキャップ、紫の本体に赤のキャップと言った具合に)。文書にすると分かりにくいが、目の前でペンを使って説明すると意外と皆納得してくれる。詳細は授業で。
2015/12/06 15:56
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
語彙力
釧路出身の直木賞作家である桜木紫乃氏の小説「霧(ウラル)」を昨日一気に読み終えた。最初は少しだけ・・・のつもりが一気に引き込まれてしまい。。。結果として夜更かししたのだが、これは作家の筆力のなせる業。さて、この小説に対して桜木氏自身はこのように述べている。「物語に出てくる野付半島で見た霧はすごく重くて、その景色はまるで“この世にあるあの世”のようでした。そんな濃い霧で先が見えない中で極道の姐になっていく珠生の姿と取り巻く人々との関係を描きました」と(日刊ゲンダイ)。最初に大まかなストーリーを決めてから取材に行くのか、たまたま目にした風景などを基にストーリーを作るのかは、作家それぞれだろうが、読後に桜木氏のコメントを見て思わず納得。というのが、題名(ちなみに、霧はアイヌ語でウラル)はもちろんのこと主要人物二人が「一蓮托生」(仏教語で、一蓮托生とは、結果の善し悪しに関わらず、人と運命や行動を共にすること。また、死後に生まれ変わって極楽浄土で同じ蓮華の上に生まれ変わること。 )という言葉が使うことなどから。作家ほどの語彙力や想像力を持つ必要もなければ、持とうとしても無理だが、ある程度の語彙力を持つことによって見える風景が豊かになったり広い視点を持てると思う。
2015/12/05 13:37
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
「質」か「量」か
最近、自分自身の環境が目まぐるしく動いていることから物事を真剣に?!考えたりすることが多い。さらには、ふと思った物事に対して再確認するような出来事が多い。11月26日は、午前中に、ある問題について結論をだした直後に全く同じ意見の人に出会った。昨日は何気に、このブログに「自分は質を重視・・・」と書いたところ、夜の授業で生徒から「先生は『質より量』、『量より質』のどっちタイプ?」と聞かれた。生徒がこのような質問をするには、それなりの理由や背景があるのだが、それはここでは割愛。結論を言うと、勉強に関しては時期に応じて「質」と「量」をうまく使い分ける必要がある。基本的なことを全く理解できていないのにむやみに「量」をやったところで、それは無駄に終わる。逆に「質重視」とばかりにひたすら解き方や公式を覚えても、それを練習する「量」をしないことには、これまた無駄に終わる。つまり、「質」→「量」へと移行するのがベスト。ン年前に指導した生徒は入試の前日までひたすらノートをまとめており…当然結果は・・・。受験直前にはたとえ「質」に不安があったとしても、とにかく過去問を解くなどして「量」をこなすべし。そう言う意味では目前に迫っている冬休みは「質」「量」ともに充実させるべくよい時期だろう。
2015/12/04 13:01
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
「職人」「商人」「商売人」
最近、複数のブログで「職人」「商人」「商売人」の違いについて述べられているのを見つけた。それぞれの見解があり、とっても興味深く読ませていただいた。と同時に自分にとっての定義は?と考えてみたところ次のようになる。「職人」とは「質を第一に考え、質のニーズにこだわるタイプ」、「商人」とは「最低限の質を保ちつつ、量のニーズにこたえるタイプ」、「商売人」とは『職人と商人』の両方の資質を兼ね備えたタイプ」だと。こう考えると一番理想的なのは「商売人」となるだろうが、むろん一番ハードルが高い(苦笑)。では、自分はどのタイプか?と言われると間違いなく「職人」タイプ。「質を第一に考える」というと聞こえがいいかもしれないが、要するにそうすることが自分自身にとって楽しく続けることのモチベーションになるから。とはいえ、「職人」にこだわりすぎると様々なことで行き詰まることになりかねず、バランスが大切、究極は「商売人」になるよう日々修行中。ちなみに自身の周囲にはというと、やはりというべきか?「職人」気質のプロが多く・・・午後からそのうちの一人がオーダー品を持ってきてくれる予定。何事もバランスが大切だと思うと同時に、「職人」「商売」「商売人」という言葉の奥深さをかみしめている。
2015/12/03 14:53
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
五里霧中
「五里霧中」という四字熟語がある。意味は「物事の様子や手掛かりがつかめず、方針や見込みが立たず困ること。また、そうした状態。五里にもわたる深い霧の中にいる意から。事情などがはっきりしない中、手探りで何かをする意にも用いる。」▽「五里霧」は五里四方に立ち込める深い霧。よく「五里夢中」と書き間違える人がいるが、先にも書いたように「五里霧の中」という意味であり、「五里」プラス「夢中」ではないことに注意。さて、勉強においても何事においても「五里霧中」という状態に陥ることは誰しも経験すること。その時にどうするか?「とりあえず一歩進んでみること」が大切だと思う。例えば、山の中で吹雪にあった。。。という場合は助けを待つべくしてビバーク(山の中で野宿)することが正解だが、林の中で霧が立ち込めた・・・としたら、いくら手を振り回したところで靄が晴れるわけではない。そう言う場合はとにかく前進してみて霧が晴れている場所をめざして歩を進めてみると、フッと霧が晴れた場所に出てくるもの。一つの解法や勉強法にこだわって、全く効果が出ず行き詰まっている時はとにかく別の方法を取ってみる、誰かにアドヴァイスをもらうなどなど取れる手段をとると解決策が見えるだろう。
2015/12/02 14:13
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
蛇の道は蛇
先日、同業者と話す機会があった。分野は若干違うが根本的な考え方や方針が一致し、ウンウンとうなずくことが多く「やっぱり蛇の道は蛇(じゃのみちはへび)【意味】蛇の道は蛇とは、同類の者のすることは、同じ仲間なら容易に推測ができるということのたとえ。また、その道の専門家は、その道をよく知っているということのたとえ。」と納得。先の諺は推理小説や探偵小説などで、少々怪しげな登場人物のセリフ中で使われることが多く、「怪しい(悪い)ことは、怪しい(悪い)者が長けている」という印象的な意味があるが、基本的には「餅は餅屋(もちはもちや)【意味】専門家に任せる・素人ではうまくいかない」とほぼ同じ意味で、類義語。詳細は割愛するが、あの場面では美味しそうな言葉を使った「餅は餅屋」よりも少々意味深な?「蛇の道は蛇」の方がピッタリくると得心すると同時に、ピッタリの漢字を使った言い回しや諺が沢山存在する日本語の素晴らしさに改めて心酔。
2015/12/01 13:00
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
レミニセンス
「レミニセンス」という言葉を聞いたことがあるだろうか?あまり知られていない言葉だが、レミニセンスとは記銘した直後よりも、一定時間が経ってからのほうがよく記憶を想起できることを表す。 レミニセンスはワード・ホブランド効果とバラード・ウィリアムズ効果に分けられる。(ワード・ホブランド効果とバラード・ウィリアムズ効果についてはここでは省略する)。なんだかよく分かったような分からないようあ言葉だが、要するに新しいことを学んだ時にすぐに身につかなくても一定時間が経って挑戦してみると出来ることあるということ。つまり、今できないからと言ってあきらめる必要はなく、とにかくしつこく?目の前の課題にコツコツと取り組むことが大切。ちなみに横文字を覚えるのが大の苦手の自分自身はというと、この「レミニセンス」という言葉を「レミ ニ センス」と分割し、料理研究家の平野レミ氏をイメージし「(平野)レミ には (お料理の)センスがある」と語呂合わせ的に覚えた。レミニセンスという言葉を知ったのはかれこれ数年前なのだが、覚える工夫をしたおかげで正しい言葉のみならず、それを覚えるに至る過程まで明確にインプットされている。とにかく知識習得に関しては、あきらめずに時間をかけて取り組むことが大切。
2015/11/30 14:15
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
小手先を変えてはいるが・・・
手作り資料が300枚近くにのぼり、ファイルが7冊目になったが、まだまだ続く資料作り。「来週はこんなイラストで、こういった内容の・・・」と計画が頭の中に浮かんでいる。さて、この300枚という数字を聞いて「え?そんなに覚えるべきことがあるの?」と思われるかもしれないが、結論を言うと国語の基本軸というのは大した数ではなく、作った資料にはかなりの重複がある。新しい知識を身につけるためには「反復」が一番なのだが、子供たちというのは単純な「反復」が苦手なので、実は本質は同じことを言っているけれど見た目は違う・・・という資料を複数作っている結果である。つまり小手先を変えながら実は同じことを繰り返し繰り返し演習するという方向に持って行っている。いかに飽きさせずに少しでもインパクトがあって楽しく出来るかと常に考えているおかげで、毎日かなりの脳の鍛錬をさせてもらっており、なんだかんだと言いながら一番楽しんでいるのは自分かな?と生徒たちには感謝。
2015/11/29 04:13
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です