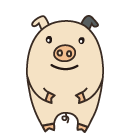小さな国語塾のつぶやき
言葉を補う
日本人は「暗黙の了解」を好む傾向がある、と昨日のブログで書いた。その典型が「小説」!余計な言葉は一切省き、登場人物の会話とちょっとした行動のみで書かれており、余韻を残しすと言えば聞こえがいいが、時として「よく分からない話だった」となることも。だからこそ小説においては言葉の中に欠けている説明を自分で組み立てる必要があり、逆に無意識に理解してしまっているところを問われた場合はきちんと言葉を補って説明することが大切となる。例えば「○○はドアを乱暴に開けて出ていったのはなぜか?」と聞かれた場合「△△と喧嘩をしたから」では不十分で「△△と喧嘩をして腹を立てているから」が正解。「喧嘩をした☞腹を立てた」の「腹を立てた」という部分を無意識に理解できてしまうのが日本人。それは素晴らしいことなのだが、落ち着いて考えてみると「腹を立てた人がすべて○○のようにドアを乱暴に開けるという行為をするか?」と言われるとそれは否。国語塾では2か月ほど前から5分ほどで読める短編小説を、4場面に分けて説明するという演習を行っているが、意外と皆苦戦している。何事も練習あるのみ!
2015/12/28 09:01
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
暗黙の了解
今日はブログを更新するのがすっかり遅くなってしまい、「あれ?」と心配された方もいらっしゃるかもしないが、元気に過ごしているのでご安心を。さて、「失敗は成功のもと」という諺を聞いて違和感を感じる人は少ない。なぜなら小さい頃から当たり前のように聞かされており「失敗した原因を突き止めることによって成功する手がかりを見つけることが出来る」という意味を知っているから。つまり、言葉の中に欠けている説明を頭の中できちんと補っているのである。他にも、論理が飛躍している次のような諺がある。「風が吹けば桶屋がもうかる」という言い回し。「風が吹くと、土ぼこりが目に入って目が見えなくなる。→三味線を弾いて生計を立てる盲人が増える。→三味線には猫の皮が使われているので猫が減る。→猫が少なくなって、増えたねずみが桶をかじる。→桶を買い替えなくてはいけない。」という論理になるのだが、正直言って論理が飛躍しすぎ。。。伝統的に、日本人は「暗黙の了解」を好む傾向があり、親しい間柄の場合はそれでいいのだが、国語で解答を作る時などは「暗黙の了解」は通じないと思った方がよい。そのことを自覚しつつ一つ一つきちんと伝えていくことが大切。自戒をこめて。
2015/12/27 17:53
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
伝え方
昨日はクリスマス、一夜明けた今日はあちこちのお店では既にお正月準備のしめ縄やお餅類が山積みに!なんて忙しい日本(笑)。さて、クリスマスと言えば日本ではすっかり「プレゼント交換」「愛を告白する日」と定着しつつあるが・・・。相手に自分の気持ちを伝える時はダイレクトに!が基本だが、上級編では「自分はナレーション」としての立場で客観的に伝えるというのものがある。上級編のコミュニケーションの達人の友人が芽室に住んでおり・・・。いつも勉強させてもらっており、思わず国語塾の授業で、いつか、模範解答として紹介したいと思っている。例えば、こんな具合に「あのね、私にはとっても大切で大好きで友人がいるの。その友人は・・・・(褒め言葉が続く)。・・・でもね、その人は○○な場合には△△のような態度を取り・・・(以前のお互いにエピソードなど)」。エピソードあたりから、実は「大切な友人」というのは「あなたのことですよ」と分かるような仕掛けになっている。むろん、この上級編のコミュニケーションは相手や場所を選ぶ必要があるが(決してビジネスにおける連絡事項などには用いないこと)、いつものは違うひねりのきいた伝え方というものを工夫すると印象度アップ間違いなし。
2015/12/26 16:31
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
沸点
誰だったかは忘れたが「勉強の習熟度」を「沸点(物質が沸騰する温度)」に例えていた。成程なあと感じる。なぜならば①人それぞれ理解をするスピードが違う②逆に冷めてしまう(忘れてしまう)スピードも違うから。ただ一つ共通して言えることは沸騰するまでは、温まりつつあることは手で触ると分かるが、目には見えないこと。プツプツと泡立ち、シューシューと湯気が出て初めて沸騰していると分かるのである。勉強もしかりで、努力している時はなかなか成果が見えづらいが必ず継続していると(ただし、正しい方法で)成果が見える。また、水は沸騰しづらいが冷めにくいのと同様に苦労して理解して身につけたことは意外と忘れないもの。また、沸騰した物質を保温しておくと長時間冷めないのと同様に、一度覚えたことを温め続ける努力(反復)することが大切。当たり前のことだが、沸騰させることすらしない、あるいは途中で火を止めてしまうことが一番よくない。寒い冬、熱く努力したいもの。
2015/12/25 17:01
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
うどんかるた
香川県が作った「うどんかるた」の「つ」の読み札「強いコシ 色白太目 まるで妻」に苦情が寄せられ、発売を延期していた問題で、県は22日、かるたを当初の札のまま、26日に発売すると発表した(朝日新聞12月15日付)。この記事を読んで溜飲が下がった。「良いイメージで受け取らない人もいるのでは」という苦情があったそうだが、そもそもどの部分が悪いイメージにつながるのかが分からない。いわゆる日本女性は「大和撫子」であるべきだという考え方の基準からすると「強い=妻」という部分が悪いイメージになるのか?はたまた最近の基準ではファッションモデルなどはみんなスレンダーのため、女性のやせ願望が強く、そのため「太目」がよくないイメージになるのか?どちらにしてもあまりにもマイナスな想像力を働かせすぎだと言いたい。そもそも、カルタ発売の趣旨としては「うどん」のイメージアップをはかるものであって、うどんの良い特長を込めた句=よいイメージの句だと言えるだろう。作品には作者の思いが込められており、それを正しく読み取ることた大切で、自分の基準で想像力を働かせすぎるのは国語を解く時ににはタブーである。国語に限らず、客観的に物事を捉えたいもの。
2015/12/24 12:51
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
かぼちゃ
昨日、22日は冬至で「かぼちゃを食べて柚子湯に入るとよい」とされている。うっかりして冬至だということを忘れていたが、たまたま午後に知人から聞き、慌てて夜にかぼちゃを食べた。かぼちゃを食べなかったからといって別になんら問題があるわけではないが、単なる縁起担ぎ。栄養価の高いかぼちゃを食べて、免疫力を高めて冬を乗り切るという意味以外に、冬至には「ん」のつくものを食べると「運」が呼びこめるといわれているから。かぼちゃを漢字で書くと南瓜(なんきん)。つまり運盛りのひとつであり、陰(北)から陽(南)へ向かうことを意味している。そんな事情から「かぼちゃは中国伝来」と勝手に思い込んでいたが、実は先日の書いたように「かぼちゃ」はポルトガル語。ポルトガル語でありながら、その由来はなんと「Cambodia(カンボジア)」の国名で、ポルトガル人がカンボジア産の野菜として日本に「かぼちゃ瓜」と伝えられたという。そして日本に持ち込まれるかぼちゃが中国の南京の港から持ち込まれることから「南瓜」と名前になったとか。人それぞれ、名前の由来があるのと同様に食べ物の名前にも由来や長い?歴史があると思うとなんだか親近感を覚える。
2015/12/23 06:34
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
すく
昨日の十勝毎日新聞に「胸がすく思い」という見出しが。捨て犬たちの里親がSNSの利用ですぐに見つかったという嬉しい内容だった。記事内容はもとより「すく」が目に飛び込んできた自分は・・・かなりの職業病(苦笑)。「胸がすく」とは「心のつっかえが取れたような、すっとした心持」のことを言う。同じく(意味は違うが)「すく」という表現を使った慣用句として「足をすくわれる」(卑劣な手段で、すきをつかれて失敗させられること)がある。ところが、文化庁の「平成19年度 国語に関する世論調査」では、「足元(下)をすくわれる」を使う人が74.1%であり、「足をすくわれる」を使う人が16.7%であったという。つまり、正しい使われ方よりも誤用が大きく上回っている。こうなると、正しく言葉を使っている人が周囲からは「間違っている」ととられかねない・・・・。言葉は変化するものだとは分かりつつも少々複雑な気分。
2015/12/22 11:30
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
混乱しそうな言葉
今日は混乱しそうな言葉を紹介する。「良いこと尽くし」(良いことばかりあるという意味)の言い回しを誤って「良いことだらけ」と使ってしまいそうだが、それは誤り。「だらけ」は「泥だらけ」「傷だらけ」「嘘だらけ」といったように悪い意味に使われる言葉であり、良いことには結びつかないから。ちなみに古書、古物店として、市場を切り開いた全国チェーンの「まんだらけ」は、おそらく「曼荼羅華(まんだらけ、朝鮮朝顔⦅ちょうせんあさがお⦆の別の名前。また、仏教においての天上に咲く四華(⦅しけ⦆の一つでもある。」の意味で使われていると想像する。決して「だらけ」がつくからといって、悪い意味の社名ではないはず。ちなみに先の「良いこと尽くし」「〜尽くし」という場合には「づくし」と書くが、「良いこと尽くめ」と表現する場合はひらがなでは「~尽くめ」は「ずくめ」と書く。まあ、ここまで細かいことを気にする必要はあまりないだろうが、せめて「~ずつ(正)」「~づつ(誤)」というルールぐらいは正しく覚えておきたいもの。人様のブログやメルマガで「ず」と「づ」の語表記があると、正直言って内容そのものの価値が下がってしまうように感じてしまう。特に不特定の相手に文章を発信するときは要注意。自戒を込めて。
2015/12/21 06:34
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
プレッシャー
来月から入会希望というご連絡を昨日いただいた。生徒さんは先日体験に来てくれた現小学四年生の二人の女の子たち。二人とも夏の読書感想文講座に参加してくれており、とってもやる気があって頑張るタイプということを分かっているので、これから毎週一緒に勉強できると思うと本当に楽しみであり嬉しく思う。と同時に、彼女たちが忙しい中スケジュールを調整しながら通塾(これは他の生徒さんにも共通)ということも重々把握しているので、なおさら、充実した時間を過ごせるよう授業計画を思案中。さて、何事も「楽しくないと続かない」と言われるし実際にそうだと思うが、さらに付け加えるならば「楽しい+良い意味でのプレッシャー(モチベーション)」があるから続くと思う。自分自身にとっては「生徒たちと一緒に勉強する楽しさ+良い授業をして少しでも彼ら彼女たちの成績をあげなくては!というプレッシャー」、生徒たちにとっては「新しいことを知る楽しさ+成績を上げたい、上げなくてはというプレッシャー」。楽しいだけではなく、プレッシャーという制限があるからこそ続く。意外と楽しいだけだと飽きてしまうだろうなあと思う今日この頃。
2015/12/20 14:59
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
制約、限定
家族への毎日の食事作り、献立を考える時に迷ってしまうという話を良く聞く。確かに家族それぞれの嗜好が違う、食事作りに費やせる時間が日によって違う・・・忙しい日は手軽に出来るメニューに限定される。そんな時は冷蔵庫にある、いわゆる「残り物、ありあわせ」の材料で何を作れるか?と考えた方が意外とすんなりと献立を思いつく。例えば、豚肉、数種の野菜があるとしたら餃子は無理だけど(餃子の皮の買い置きがないため)肉団子ならOKと言った具合に。作文では何を書いたらいいか分からない・・・・という場合は先の献立と似たようなことが言える。まず「題名や、どうしても書きたい外せないエピソード」だけを決めること。そして次にそれを中心にしてメモや構成を作っていくと、かえってスラスラと書ける。つまり「制約」「限定」を加えることで、かえってゴールが見えてくることがままある。決してあれもこれもと欲張りすぎないことがコツ。小学生は2学期終了を目前なので、「2学期に頑張ったこと」などが課題となっている学校がある。先に述べたことを意識すると読み手に伝わる文章を書けること間違いなし。
2015/12/19 03:20
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です