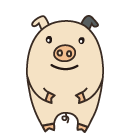小さな国語塾のつぶやき
ホトトギス
「猿」と呼ばれていた有名人と言えば豊臣秀吉、豊臣秀吉と言えば「鳴かぬなら鳴かせてみようホトトギス」という句が有名である。が、この名は、江戸時代になってからたくさん登場した物語の『太閤記』が記するもので織田信長は秀吉のことを「禿ネズミ」と呼んでいたという記録がある。また、織田信長(「鳴かぬなら殺してしまえホトトギス」)、豊臣秀吉、徳川家康が(「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」)実際の句を詠んだわけではなく、江戸時代後期に書かれた「甲子夜話」という随筆に出てくる句で、3人の人柄を比喩的に表現している。人間の個性についてはどれが正解といったことはなく、先ほどの「ホトトギス・・・」についても、どれも一理ある。が、勉強においては間違いなく豊臣秀吉の方針を取るべきであることは誰もが認めることだろう。織田信長のようにさっさと諦める、家康のように暢気に待つ・・・なんてことは勉強においてはありえない。例えば、株投資などにおいては有りだろうが。今できることを工夫してする!という心掛けを見習いたいもの。
2016/01/07 07:30
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
申
7日までは、まだまだお正月・・・、というわけで今日も「申(さる)」の話題。申とは元々は雷の象形文字、雷は天にある神の威光のあらわれと考えられたので、「神」の字に使われる。また、雷(稲妻)はまっすぐに落ちることから、「紳」(ふとおび。からだをまっすぐのばすおび。転じて、高官が用いる礼装用の太いおび。 地位・教養が備わったりっぱな人。インテリ。知識人。)や「申す」「伸びる」という字に用いられるようになった。では、いったいなぜ「申」が「猿」に?実はこれは単なる当て字。読み方が同じ字を当てただけ。中国を中心とした東アジアの世界では、子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥の十二支を使って暦、時刻、方角を表した。数字でもなんでもない漢字の順番を覚えるの大変なので、神様に新年の挨拶に来た十二種類の動物になぞらえて十二支に宛てて覚えたとか。そんなこんなでたまたま「申」を「さる」と読むことから「猿」が当てられた。🐵には「伸びる」という意味はないけれど、まっすぐに伸びる一年にしたいもの。
2016/01/06 00:12
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
断腸の思い
今年は申年ということで、ラジオ番組では高崎山自然公園の飼育係の方がゲストで「猿」の生態について語っておられた。人間は猿よりも賢いと思っているため、何かと上から目線で見てしまいがちだが、実は猿から学ぶことが多いという。その代表的なことが「子育て」。猿は子ザルをたっぷりの愛情を込めて育てつつも、厳しくするべき時は厳しく、そしてほどよい距離で子供を見守っているとか。長年、猿の生態を観察している方のコメントはとても説得力がある。さて、「断腸の思い」という故事成語がある。意味は「はらわた(小腸のこと)がちぎれるほどの大変つらい思い」で、由来は「晋(しん)の国の桓温(かんおん)が船に乗って谷を過ぎる時に、その家臣が猿の子どもを捕まえた。母親の猿が子どもを追って百里あまりもついてきたが、家臣は子どもを殺してしまった。これを見た母親の猿は泣きさけんで死んでしまった。その腹をさいてみると、腸がちぎれていたことから、この語ができたという。猿の母の愛情の深さ、さらには腸がいかに動物の精神とつながっているかを物語っている故事成語だと言える。それにしても、3~4世紀に猿の生態、腸の大切さを既に知っていたと思われる中国文明・・・・侮ること勿れ。
2016/01/05 00:28
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
現代版福笑い
「笑う門には福来る(いつも笑顔を絶やさない門〔もん=一族、一家族〕には自然と幸福がやってくる、ということわざ。)」とはよく言ったもの。出来ることならば年始早々、楽しく笑いたいもの。昔のお正月の遊びの一つに「福笑い」というのがある。福笑いは顔の輪郭を描いた紙と、その輪郭に乗せる切り抜いた顔のパーツ(眉・目・鼻・口)を使って遊ぶ。布などで目隠しをされた者が切り抜いた眉、目、鼻、口などを正しい位置(と自分が思う場所)に並べていく。絶対的な勝ち負けなどは特になく、その時々で「正確な位置に置いた者の勝ち」「面白い顔を作った者の勝ち」などというように勝敗を決めたりする。自分自身が「福笑い」をして遊んだのはもう何年も前の話で、最近では「福笑い」の道具を目にすることすら少ない。が、が、が、現代版福笑い?なるものを発見し、思わずパソコンを見ながら大笑いしてしまった。道内在住の友人(刺繍作家)がブログ内(「イトヌリエ」でヒット。1月2日付のブログ)で、製作途中の作品を「顔」と表現。友人の息子さんはそれを“笑顔”と捉え、友人は“マスカラが溶けた黒い涙の人”ととらえた。ちなみにその作品というのは雛祭り用の壁掛け・・・。確かに奇妙な顔に見えなくもない・・・が、片や笑顔、片や涙…その作品というのは自身がオーダー中の作品。画像と記事の両方に思い切り笑わせてもらった。友人も書いているように、同じ「顔」ならば「笑顔」の方がいい!年始に思い切り福笑いをして楽しい雛祭り・・・を迎えたいもの。3月の雛祭りまでに作品を仕上げてもらう予定なので、ご覧になりたい方は2月下旬~3月上旬に国語塾までお問い合わせを?!(その前に友人のブログでも紹介されるかも)
2016/01/04 00:42
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
見ざる言わざる聞かざる
以前、知り合いの保健師さんが次のようなことを言っていた。「あるお母さんが、育児書を沢山読むと逆のことが書いてあり混乱すると言うの。育児書を読みすぎるのも問題よね」と。これは育児のみならず健康法、勉強法すべてに当てはまることだと思う。というよりもすべての人間に当てはまる方法なんて存在せず、またその時々によって選択すべき方法というのがある。例えば、じっくりを理解できるまで国語の問に取り組むことは大切だが、中三生がこの時期になってまでそんなことをやっているのは言語道断。極端な話、取捨選択をして超苦手な分野は捨てる覚悟を持つことが大切になってくる。色んな人が色んなことを言うが「見ざる🙈言わざる🙊聞かざる🙉」を実行すべき。むろん、独りよがりではなく、自分にとってベストのアドヴァイスを取捨選択するということ。今年は申年!複数の方法があったら、楽しい方を選んでそれ以外は「🙈🙊🙉」を実生活でも実行予定。←今までもそうだったでしょう?ますますエスカレートするの?という声が聞こえてきそうだが、早速その意見は「🙉」(苦笑)
2016/01/03 00:00
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
年始の意宣り
人様にプレゼントするときには「自分では買わないけれど、もらうと嬉しい物」というコンセプトでチョイスしている。お正月の恒例挨拶の年賀状もそれに近いものがある。書くのは面倒だが、人様から送っていただくと最高に嬉しい。年に一度の挨拶で何十年もつながっているご縁もあり、お互いに相手の変化を喜んだり悲しんだり。今年は数年ぶりにご縁が復活した方から年賀状をいただいたり、ン十年前にお世話になった恩師から今年も年賀状を頂き、そこに「素敵な温泉があれば北海道に行きたい」とあるのを真に受けてみたり。近々、十勝のおすすめ温泉のリスト方々、手紙でも書いてみようかと真剣に考えている。生徒に「手紙の書き方」を偉そうに指導するだけではなく、まずは自分が実践!そう考えると年賀状というのは「手紙を書く」「付き合いを復活」にはちょうどよいきっかけになると思う。日本における年賀状の起源ははっきりとは分かっていないそうだが、今のシステムを整えた郵政局、年末年始を不休で頑張って下さっている職員の方々に感謝しつつ心を込めて年始早々、手紙をしたためてみようというのが自身の年始の宣言(意宣り)である。
2016/01/02 00:58
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
四苦八苦
いよいよ新しい年の始まり!今年もよろしくお願い致します。さて、このブログを除夜の鐘を聞きながら書いている・・・。除夜の鐘は多くの寺で108回撞かれる。この「108」という数の由来については複数の説があり、格別にどれが正しいということはないが一般には煩悩説が有名である。仏教用語で「四苦八苦」というのがあり、そこから4×8+8×9=108だとか。「四苦八苦」の意味は「非常に苦労すること。たいへんな苦しみ。もと仏教の語で、あらゆる苦しみの意。」▽「四苦」は生しょう老・病・死の四つの苦しみ。「八苦」は「四苦」に愛別離苦あいべつりく(親愛な者との別れの苦しみ)、怨憎会苦おんぞうえく(恨み憎む者に会う苦しみ)、求不得苦ぐふとくく(求めているものが得られない苦しみ)、五蘊盛苦ごうんじょうく(心身を形成する五つの要素から生じる苦しみ)を加えたもの。さて、自分自身はというと煩悩は108どころかもっとあるのでは?と思わず苦笑い。ただ、言い方を替えると煩悩があるからこそ前に進めるのだとも思う。煩悩だらけで身動きが取れなくなっては元も子もないので、ある程度の煩悩は除夜の鐘共に手放しつつ今年も頑張って仕事をしようと今からワクワクしている。ぜひ温かい応援をよろしくお願い致します。
2016/01/01 00:23
-
ゆかぽんさん!!!!新年早々、素敵なコメントありがとうございます!本当に本当に嬉しく、励みになります。お互いに今年も素敵な良い年になりますように!
2016/1/2 00:43 返信
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
晦日
今日は一年最後の一日で、大晦日。「晦」という文字は「くらます」とか「くらい」という意味があり、月(暦月)の終わりの日には月がどこかに姿を「くらまし」ていて、月が姿をくらましているから夜は「くらい」という。月が出ているか隠れているかによる暗さなわけで、日暮れ、夜明け前といった一日の時間帯を指すわけではないが「暗い」ということには変わりない。さて、「夜明けが一番暗い」という有名な名言がある(苦難の期間は、終わりかけの時期が最も苦しく、それを乗り越えれば、事態が好転するだろうという意味)。こちらは一日の時間帯をさしているわけだが、どちらにしても月が隠れてしまっても必ずまた月が出て来て明るくなる、また「明けない夜はない」のであって必ず明るくなるという点においては共通。一年間、大変だった方もそうではなかった方も共に明るい新年を迎えていけることを信じている。自身に関しては、素晴らしい方々に恵まれて本当に楽しく仕事をさせていただいた一年だった。来年はもっともっと明るく輝くよう気持ちを新たにしている。一年間本当に本当に感謝。
2015/12/31 08:53
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
意宣る(いのる)
役所勤め、会社勤めの方々は28日が仕事納めで、正月休みに入ってるだろう。かくいう自身も28日が仕事納めで、それ以降は自宅で自分のペースでの仕事をしている。逆に年末年始になると忙しくなる職業の方もいるわけであって、代表的な職業?!が神社関係。年末年始の準備、12月31日には「年越しの大祓」年始には「初詣」「どんど焼き」と行事が続く。自分自身はこれといった思想を持っているわけではないが、一年間の感謝と決意を述べるために毎年必ず年始に氏神様へのお参りは欠かさない。神社へのお参りというと「祈願(神様にお願い)」することが多かったのだが、最近は先にも書いたように「去年無事に過ごせたことへの感謝と、新しい一年の決意」を心の中で述べている。そもそも「祈る」とは「意を宣(の)る」が語源だとか。つまり、意を述べる、宣言することから「意宣る(いのる)」で、実は決意表明なのだ。神様の前で神聖な気持ちで決意を述べると、そう簡単にはあきらめたり、いい加減なことが出来ないような気がするので、最近は毎年の恒例としている。
2015/12/30 00:20
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
ピンチはチャンス
今年もいろんな出来事があったが、映画業界では平成15年は「4D映画」を楽しめる映画館が急増し「4D元年」と言われる年だった。視覚効果にとどまらず、シートからの振動・水しぶきといった効果によりリアルな鑑賞体験を可能とする体感型(4D)シアターを導入する劇場も増えているとか。自身はまだ体験したことがないが、ネット上のコメントを見ると・・・かなりすごいらしい。なぜ映画業界がここまで進化したか?自宅でDVDを楽しめるようになり、映画公開後、しばらくするとすぐにDVDが発売となるため「わざわざ映画館に行かなくても・・・DVD発売まで待とう」という人が増え、映画館が斜陽化してきたから。逆に言うと映画業界を脅かすDVDの出現というピンチが映画業界に工夫をもたらす結果に。今年も残すところわずか・・・。学生にとっては、一年の学習ぶりを反省して来年、次学年へのステップへと備える時期。今年一年、ウナギのぼりに成績が上がっている、上がりつつあるならば問題ないのだが、その逆の場合はというと・・・言うまでもないことだが、あらゆることを見直すべき時期。ピンチはチャンスへの工夫が隠されていると信じて前進。映画業界が斜陽とはいえロングセラーといった普遍的な作品が好調なのと同様、普遍的な学力の基礎力は侮るべからず。
2015/12/29 22:38
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です