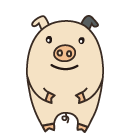小さな国語塾のつぶやき
「なぜ?」という質問
国語が苦手と一言で言っても、いろんなタイプがある。例えば長文を読むのが苦手、漢字が苦手、古典が苦手、詩や短歌が苦手などなど。苦手克服のためには当然「勉強」「演習」ということは誰しもが分かっていることだが、ただ単にやみくもに演習するだけではなく、なぜ苦手なのか?という理由を考えることで、今何をすべきかが見えてくることが多々ある。「なぜ長文が苦手なのか?」→「何を書いているか分からないから」→「なぜ何を書いてるか分からないか?」→「難しい言葉が出てくるから」→「ではどうするか?」→「長文を大きく3パターンに分ける」→「それぞれの対応策を実行してみる」→「それぞれの対応策は?」→「国語塾で配られたプリントなどを参照」。つまり、苦手だから勉強するぞーと張り切ったところでいきなり難しい問題を目の前にしたところで・・・一気にやる気が失せてしまう結果に。それはまるで地図を持たずに初めての道順をたどるようなもの。特に苦手としている物事に取り組むときは、「なぜ?」「ではどうすればいい?」と自問自答をしてから取り組むことが長続きさせることへの近道。
2016/01/19 14:40
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
聴き取りポイント
国語塾で小学生対象に行っている聴き取り練習には様々なバージョンがある。例「お話のどこがちがう?」(ア、イの二種類の短い文章を聞いて間違い探しをする)「迷路」(右、左、上、下の指示に従って進む)「書きとり」(長い文章をそっくりそのまま書きうつす、意味のない言葉をひたすら書き写し、最後に暗号を解く)などなど。これらは一例で、まだまだある。さて、意外と難しいのが一番最初の例で挙げた間違い探し。アの文を真剣に覚えようとしたり、きちんとメモしようとすると、時間不足で放送がどんどん先に進んでいく。では、どうするか?ポイントは「集中しすぎないこと」「キーワードだけを記憶にとどめるようイメージする」の2点。どんなことに対してもそうだが、一点に集中しすぎるとそれ以外が手薄になってしまう。例えば、ア「昨日、私はおばあちゃんの家まで、妹と二人だけで行きました。おばあちゃんの家はここから電車で20分くらいに行ったところにあります。」という文章の場合、「おばあちゃんの家、妹と、電車、20分」の単語だけメモしたり頭に印象付ける。主人公は私で、特定の名前の人ではないのでさほど意識せずにそれ以外の数詞や名詞をチェック!ちなみにイの文章としては「30分⇒20分」となっている。これは口で言うよりも実際に体験していくうちに必ず身につくことなので1、2回できなくても問題ない。先に書いたことを意識すれば1か月もすれば見違えるようにどの子も上達するのでご安心を。
2016/01/18 14:50
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
縦書きの勧め
最近はパソコンやメールの普及で、文章の横書きが多くなってきた。実際にこのブログも横書きなわけであって・・・。ただし、自分で文章の下書きをしたり添削するときは、縦書きがお勧め!なぜかというと縦書きと横書きでは視野の差があり、横の方が視野が広いから。人間の二つの目が横並びなので、横書きでは横長の視野が見にくくなり、縦書きでは、円形に近い視野になるそう。左右共に視野は100度だが、上下では上60度、下70度。つまり、同じ文章を同じ面積の中に書いた場合、横書きでは1行読むのに目の移動が3回。それに対して、縦書きでは2回で済むという具合になるのである。実際に試してみると、実感できるだろうし、自分自身においても横書きの物だと読み落としをしてしまうことは多々ある。むろん、日本人にとっては縦書きが長らくの習慣になっているからという事情もあり、なおさら先のようなことが言える。親しい人に送る手紙やカード、ビジネスにおける名刺などは横書きの方がオシャレだと支持されることが多いが、文章を書いたり読んだりするときは、視野の広さを考慮し、ぜひ縦書きを勧める。
2016/01/17 16:50
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
合力
「合力」と聞いて皆は何を思い浮かべるだろうか?おそらく理科の「2つ以上の力を合成した力」と定義し、小型の辞書もそれくらいの意味しか載せていないだろう。が、実は日本には昔から「合力」という言葉が存在し、古典の時代にはコウリョクと読ませ、「力を添えて助ける」意を有した。室町時代初期の『義経記(ぎけいき)』にも「三日がうちに浮き橋を組んで、江戸太郎に合力す」と出てくる。源頼朝が隅田川を渡ろうと江戸太郎(重長)に浮き橋を組ませた折、葛西三郎こと葛西清重が合力した、つまり助勢したというのである。また、明治期に大森貝塚を発見した米人モースは、江ノ島で過ごした経験を次のように書き留めている。「人力車夫や漁師達は手助けの手をよろこんで『貸す』というよりも、いくらでも『与える』」(東洋文庫『日本その日その日』)。近代日本の庶民に合力の精神が広く浸透していたことがうかがい知れる。皆が嫌う古典。昨日も某中学生に「平家物語を解こうか」と声をかけた瞬間にブーイングを飛ばされてしまったが、実は国語の知識としての勉強のみならず古典を勉強することによって日本人気質の素晴らしさを学べることこそが、自分自身が古典を愛する所以である。ただ、そんな暢気なこと?を言えるのは、訳わからない暗号のような古典を目の前にして四苦八苦し、克服したという中学生時代があるから。
2016/01/16 11:02
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
かぶく者
ちょうど去年の今頃、生まれて初めて生の歌舞伎を楽しんだ。以来、すっかりはまってしまい、必ずまた観劇に行こうと張り切っている。さて、「歌舞伎」の語源は元々「かぶく(傾く)」の連用形「かぶき」が名詞化したもので、「かぶき」に歌・舞・技を当て字にしたという。「かぶく」の「かぶ」は「頭」の古称といわれ、「頭を傾ける」が本来の意味であったが、頭を傾けるような行動という意味から「常識外れ」や「異様な風体」を表すようになった。⇒そこから転じて、人生を斜(しゃ)に構えたような人、身形(みなり)や言動の風変わりな人、アウトロー的な人などを「かぶきもの」と呼んだという。つまり日本の伝統芸能の歌舞伎の元々の語源はあまりいい意味ではなかったということになる。少しショックだが、人と違う才能を持っている人、格好をしている人はどうしても目立つため、特に昔の日本人にとっては異端者として映ったのだろう。でも、たんなる変人なのかそれとも実は天才なのかは明確に線引きすることは出来ず、また時代によって、その時代が求める逸材の中身が違ってくる。もしも人と違った発想、気質を持っているならば、それらをマイナスにとるよりも時代を先取りしている?と発想を少し転換するのも面白いかも?!
2016/01/15 11:34
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
スピード
昨日から新規で小学生クラスを開講し、小学4年生の女の子2人が張り切って来てくれた!2人とも夏休みの読書感想文の講座を受講してくれたことも有り、お互いに性格などを分かっているため(自分自身にとっては、彼女たちが、いかにヤル気があって頑張り屋さんかを分かっていた)事前から楽しみで、実際の授業も本当に楽しくさせていただいた。で、ここからが本題。二人以上を同じ空間で何かの作業をする時には、当然スピードの差が出てくる。大人がそばについている場合だとついつい「待たせては申し訳ない」という意識が働くため、自分の子が遅いと焦ってしまうことがある。また、授業や講座の場合は時間が限られてしまうため、途中で作業を中断させられる場合も多々ある。が、ここで声を大にして言いたいのは「遅いから駄目ということではない」ということ。むろん早くて内容も完璧と言うのが理想だが、なかなかそうはいかない。逆に自由作文などにおいてはじっくりと取り組むことによって名文が出来ることもあるし、問題演習においても小学生のうちは、まずはじっくりと取り組んで内容や教わったことを自分の中で反芻してから取り組むことが大切になってくる。それを繰り返していくうちにだんだんスピードは上がっていくもの。焦らずに着実に!
2016/01/14 13:40
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
塾ジプシー
久々のブログ更新、と同時に久々のネット活動。携帯はガラケー、タブレットなども持っていないため何日か外出する時はネットから無縁の生活になる。それはそれで非日常を体験出来てよい時間(と言いながらも頭の中は常に仕事のアイデアでいっぱいだが・・・・)。さて、3日ぶりにネットを開くと国語塾へのアクセスが増えており、びっくりするやら嬉しいやら。連休明け、夏休み明け、冬休み明け、さらには定期試験明けになるとアクセスや問い合わせが増え、何人かは入塾と言う運びに。別の塾を辞めてきてくださる方もいらっしゃり、なんとか国語に興味を持ってもらい成績アップをとこちらの気持ちも引き締まる。正直言って、どの塾も使っているテキストに大きな差はなく、下手すると同じテキストを使っているということも。では、何を基準に塾を選ぶか?①指導者の教え方が分かりやすいか(本人にとって)②塾の方針が合っているか(本人、保護者にとって)の二点に尽きるだろう。意外と見落とされがちなのが②、本人は何となく通塾しているが・・・・保護者に取って不安材料が生じたらすぐに動いた方がいいだろう。塾ジプシーのようになってしまって入試に間に合わなくなると困るので、自分にぴったりの塾を見つけてほしいものだと客観的に思う今日この頃。むろん、選択肢の一つとして当塾を入れていただければ幸いである。
2016/01/13 11:31
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
自己肯定感
長年、勉強を教えていて感じることが「自己肯定感が低いタイプは伸びない、伸ばせない」ということ。むろん、個々人の生まれつきの能力の差というのがあり、伸びしろがそれぞれ違う。伸びしろ、キャパシティが少ないタイプに限って自己肯定感が低い⇒素直に指導者の指示に従わない⇒できない問題、宿題をやっていないことに対して言い訳したり、「宿題をやったけれど持ってくるのを忘れました」と言う(本当はやっていないことは顔を見た瞬間に御見通し)。こちらとしてはキャパシティが元々少ないタイプこそ、なんとか伸ばせるところまで伸ばしたい、そのお手伝いをしたいと思うのだが・・・。これは、学校教育というものが、点数でその子を判断したり、競わせることで人の価値を判断しかねないようなシステムになっていることに原因があるのか?むろん競争それ自体が悪いわけではないのだが、競争によって「人の価値」が決まるという風に考えると、これは問題か。ちなみに心理学の実験でもすでに明らかになっていることだが、「何か失敗をしたとする。そのときに、自分を責める人と自分を励ますことができる人、どちらが次の行動にうつることができるかというと、自分を励ます人。」根拠のない楽天思考はよくないが、自己肯定感を下げて卑屈になることは避けたいもの。※今日から留守にするので、ブログは明日から二日間お休み。水曜日から再開予定!講うご期待?!
2016/01/10 01:57
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
連想法
昨日は中学生クラスの新年初の授業。新年ということで、旧暦を学習内容に取り入れた。中学2年生の生徒たちは「学校では習ったけれど、半分ぐらいしか覚えていない」「頭文字さえ、言ってもらえれば書けます」とのこと。当然中1生は初めて聞く内容でポカーンという状態。そこで、彼らの要望に応えて?!頭文字を利用した連想法のプリントを配り、さらには別のエピソードを2,3紹介した(詳細は企業秘密なので…笑…略)。さらには七草をすべて言えるかどうかを確認したところ・・・・最初は全問正解は無理だったので次のような連想を提案「箱(はこべ)の上に仏さまが坐ってる(ほとけのざ)。手には白い鈴を持って(すずしろ、すずな⇒なずな…しりとりで関連させる)いる。すると勤行している人(ごぎょう)がせりよってきた(せり)」。最初は連想することが難しかったのだが、イメージが定着するとすらすらと7つを言うことが出来た。英単語や漢字などは目で見て、意味を考えて覚えて、紙に書いて確認する必要があるが、同じグループの物を覚える時などは連想法がお勧め。連想するのが難しい!と躊躇するタイプもいるが、やってみて慣れると意外と簡単に出来るようになるのでぜひお試しを。
2016/01/09 11:18
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
黄泉(よみ)
人それぞれ好みの色があると思うが、自分自身は黄色が好きである。偶然にもHP用の写真を撮った時に来ていた時の服も黄色。ある日、ふと気づいたのだが、死後の世界を表す「よみ」という言葉は「黄泉」と表記される。「これって縁起悪い~?!」と思ってなぜ、黄という字を使うのかを調べてみたところ次のような答えが。「黄泉という漢字表記自体は本来、古代中国人が考える死者の世界を表すものだったようです(この場合は「こうせん」と読む)『黄泉』というのは『地下の泉』という意味なのだそうです(黄は五行の考え方で「土」を表す。黄色のことではない)。」(民俗学ひろいあげ辞典より抜粋)一方、日本人には日本人の考える死者の世界があり、こちらは「よみ」で、おそらく日本に中国の思想が入ってきたときにこの「黄泉(こうせん)」も入ってきて、それが「よみ」と同一視されて当て字として「黄」が使われるようになったらしい。つまり、「黄」という字は色としてではなく「土、地下」という意味で元々は使われていたものを、日本人が当て字として使用したということか。成程、知れば知るほど奥が深い漢字。そう言えば年賀状で、昔の友人が算命学(中国由来の中国に発祥した干支暦をもとに、年と月と日の干支を出して、 人の運命を占う中国占星術、中国陰陽五行を土台とした運命学の一流派であり、伝統を 継承しながら日本で学問として大成された。)を学び、仕事して頑張っているということを知った。自分はそちらの方向に行くつもりは全くないが、チャンスがあれば友人から色々とレクチャーをしてもらおうと楽しみである。
2016/01/08 16:12
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です