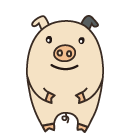小さな国語塾のつぶやき
小説の前書き
人と知り合う時には極力、色眼鏡で見ないように、客観的に判断したいと常日頃心がけているつもりで、基本的に人のうわさ話などには全く興味がない自分自身(単に、人付き合いが悪いだけ?!)。だが、時と場合によっては前もっての情報が重要なカギを握ることがある。例えば、体質的に受け付けない食べ物がある場合だと相手にそれを知らせておく必要があるなどから、診療所や病院では必ず前もって問診がある。それは相手のことを値踏みするのではなく、お互いにベストの方法を取るために必要なこと。それと同じことが国語の小説でも言える。長い小説の一部だけが国語の問題として登場するわけであって・・・。どういう状況かの説明が、小説問題の前文として2,3行ほど書かれていることがある。それが、本文に比べて小さい字で書かれていることもあって、意外とさーっと読んでスルーしてしまいがちだが、実は問題を解く上でのかなりにヒントになるうる!今週は小学生、中学生共に小説の前書きありの演習をしており、実際に如何に前もっての情報が大切かを実感してもらっている。侮ること勿れ!小説の前書き!
2016/01/29 14:47
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
金閣、銀閣
世の中には紛らわしい言葉が多く、迷うことが多い。中学1年生のMちゃんが「先生、社会で『銀閣寺』と書いたら×でした。答えは『銀閣』でした。どう違うんですか?」との質問。思わず、え?銀閣寺でダメなの?!と思いつつも「社会では金閣、銀閣で覚えておこうね~」と言葉を濁した。その後、あれこれ調べてみると「銀閣寺」とは、1490年に足利幕府八代目将軍の足利義政によって創建された寺で、正式名称は慈照寺(じしょうじ)。一般的に「銀閣」と呼ばれる建物は慈照寺の観音殿(かんのんでん)で、黒漆塗の外観をしているとのこと。つまり、よく目にする茶色っぽい建物の写真を何というか?と聞かれたら厳密には、観音殿なので「銀閣」と答えるのが正解と言える。ただ、問題集などによっては「足利義満が建てたもの⇒金閣寺、足利義正が建てたもの⇒銀閣寺」のように「寺」を入れてもOKとなっている。要するに厳密な線引きはないようだが、ちょっとしたニュアンスの違いで点数を落とすのはもったいないので、「金閣」「銀閣」で覚えている方が無難か。ちなみに三島由紀夫の小説は「金閣寺」である。要注意。
2016/01/28 14:33
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
3
最近読んでいる新刊は『「3」の思考法(斎藤孝著)』。3を基準として物事を考えたり進めるとうまくいくという内容。たとえば・長いレポートも「3章」で考えれば書ける。・一週間を「3分割」して嫌な仕事は月、火に、などなど。成程、3と言う組み合わせが一番安定し落ち着く場合が多く(人間関係における三角関係はごめんこうむりたいが)色の三原則、雛祭りの菱餅も3色、3つの標語(例えば、ビジネス社会で使われる「ほう(報告)れん(連絡)そう(相談)」)などが挙げられる。また、人間は3回プッシュされるとその気になるという話を聞いたことがある、そのためCMは頃合いを見計らって3回流すとか。また、相手をその気にさせる時は3回繰り返すとよいと言われる。例えば、異性をほめることによって自分に意識を向けさせる時に一回目の「美人だね(かっこいいね)」と言う言葉には相手は「は?お世辞?」、二回目で半信半疑、三回目で本気になるという。(ただし、お世辞の場合はすぐに見破られるので要注意)。そんなこんなで「苦手」「無理」という内容もとりあえず3回を意識して学習することをお勧めする。漠然と「繰り返さなくては・・・」よりもまずは「3回」と具体的に数字を掲げると少しはモチベーションが上がる?!
2016/01/27 15:12
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
国文法
国文法は難しく、「国文法大好き」「楽しい」というタイプは未だかつて見たことがない。かくいう自分自身も中学時代に最初は四苦八苦したことを今でもよく覚えている。さらには、「必死でやったにも関わらず全滅した・・・」となりやすい単元でもある。では、なぜ必死で勉強したにも関わらず全滅しやすいか?結論を言うときちんと理解していなかったから⇒なぜ理解できていなかったか⇒学校のプリントやワーク類演習の場合、動詞は動詞ばかり、形容詞は形容詞ばかりで沢山演習するため、分かったような気分になるから。つまり、最初の基礎練習はむろん絶対不可欠だが、その後に必ず融合問題を解く必要がある。とはいえ融合問題を解こうとした瞬間に「全く分からない」「嫌だ」→「だからやらない」→「いつまでも出来ない」という悪循環に。その悪循環にどっぷりとはまってしまっていた中学2年生のS君。文法といった瞬間に「嫌だ!苦手」とフリーズ。先週の授業で大切なポイントを3つ強調し、一緒に演習をしたところ授業が終わる頃には「文法、楽しいかも~」とまで言うようになり、教える側に取って最高の言葉のプレゼント。国語授業でどんな魔法を使ったか?実は魔法などはむろん使っておらず、大切なポイント3つ+本人のやる気。文法で全滅・・・という経験は少なからずあるもの。そこでふてくされずに奮起するかが文法を克服する一番の大切な要素か。
2016/01/26 13:38
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
寇
先日、中学生の授業終了後に中一生徒3人がお互いに「浄土宗は誰?」「法然」「親鸞は?」などなどとお互いに問題を出し合っていた。ちょうど学校で鎌倉、室町のあたりを勉強しているようだ。さて、鎌倉幕府がほろんだきっかけとなった「元寇(げんこう)」〈文永11年(1274)と弘安4年(1281)に、元のフビライの軍が日本に攻めてきた事変。蒙古来(もうこらい)。蒙古襲来。 大辞泉 より〉、日明貿易の時に「倭寇(わこう、海賊という意味)」が暗躍したと習うが、その時の「こう」は「寇」という字を用いる。うっかりすると「冠」と間違えそうになるが、要注意。「寇」という字は先の二つの熟語以外ではほとんど目にすることがないが、一体どんな意味があるのかを知らエべてみた。すると「戦いでとらえた敵を廟に連れて来て、元(頭)に攴[ぼく](打つの意味がある)を加えて呪いをかける字」「寇[こう](あだする、かたき)で、敵、外敵の意味がある。大辞泉より」らしい。成程~、やはり「寇」には意味があったんだと納得。次回の授業では「寇」の意味と「冠」と書き間違えないよう、彼らに伝えようと今から楽しみ。
2016/01/25 14:47
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
鍼
「鍼・灸」という看板を時々見かけることがあり、幼い頃はそれを「げん・きゅう」と読み違えており、大分経ってから「はり・きゅう」と読むことを知った。(※「鍼」とは身体の特定の点を刺激するために専用の鍼を生体に刺入または接触する治療法。中国医学のの古典的な理論に基づいている。)「鍼」は当用漢字にないため公的には「はり灸」と表記されるそうだ。なぜ「鍼」を「げん」と読み間違えたか?想像がつくと思うが、「減」の形声文字だと思い込んでいたから。それにしてもなぜ「鍼」と書いて「はり」と読むのか気になったので早速調べてみた。「咸」の音読みは『カン』が『ゲン』、戉(まさかり)で人を脅して口を閉じさせる様子を表す会意文字。漢字の足し算では戉(まさかり)+口=咸(まさかりでショックを与えて口を閉じさせる。)意味は『口を封じる』、『口を閉ざす』となったという。つまり、金(金属)+咸(刺激する)=鍼(金属製の鍼で人体を刺激して治療する。鍼。はり)という会意文字だと知り、長年の謎が解けて何となく誇らしい気分?!突然「鍼」の漢字を取り上げたのには理由がある。先日、友人とのメールのやり取りの中で、友人が高校生の頃に諸所の事情から鍼治療をしたことがあることを知った矢先に1月23日付の十勝毎日新聞で「お灸カフェ」の紹介があったから。幸い、自分自身は現在、体の不調を抱えているわけではないので鍼灸にお世話になることはないが、今後チャンスがあったら試してみるのもいいかも?と思っている。
2016/01/24 05:49
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
漢文の決まり
古典と言えば漢文と古文。指導者、中学生共に「漢文と古文だったら、漢文の方が簡単」という意見の方が圧倒的に多いだろう。かくいう自分自身が中学生時代も同じことを感じており、現在もその考えは変わっていない。なぜ漢文の方が簡単かというと暗記するべきことが少ないから、最低限の決まりさえ覚えれば普通の現代文と同じように解けるから。が、ここで落とし穴が。最低限の決まり(返り点、書き下し文にする際には送り仮名はひらがな書きにする、など)以外でも覚えておきたいことが二つ。①「不(ず、ざ)」「也(なり)」「耳(のみ)」という助動詞、助詞はひらがな書きにすること②「而」「於」といった置き字は書かないという二点。この二点はわざわざ覚えなくても、問に注釈として「『不』はひらがな書きにすること。『而』は書かない」と載っているが、本文の傍線部を書き下し文にしようと必死になっているうちに、いつのまにか注釈の内容が頭からすっぽりと抜けてしまうもの。それゆえに、注釈があるなしにかかわらず、最初から先の2点は決まり事として頭に入れておいたほうが無難。自分の記憶に基づいて書き下し文にしつつ、さらには注釈で確認すると言った具合に。実際に昨日の中学生クラスで注釈に色を付けて目立たせた上に、二点の決まりを紹介した後に演習を行ったが・・・初めて取り組む漢文だったため一年生はうっかりミスが相次いだ。結局は頭で理解したことを実践して自分のものにすることが大切。
2016/01/23 03:15
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
願い
ある生徒から「長年の願いがかないました!」と言う連絡が!その生徒とは、「もしも願いが叶ったら○○してお祝いしようね!」と約束していたので、○○について具体的に構想を練っている今日この頃である。さて「願い」という言葉の語源は「ねぎらい」だそうだ。「ねぎらい」という言葉を辞書で引くと、「相手の努力に対して感謝の意を表すこと」とある。まさに生徒の願いが叶うことは、自分自身にとっては「相手の努力に対して感謝の意を表すこと」に他ならない!たまたま調べた「願」という字の語源が、今まさにぴったりの状況なのには(@_@)!自分自身は、生徒の願い(勉強ではない)に対しては、ただただ陰から応援することしかできなかったので本当に手放しで嬉しく、本人の努力には感謝しかない。さて「願いが叶う」以外の表現としては「夢が叶う」があるが、「夢」と言う字は「いめ(寝目)」が語源で「夜寝ている時に見るもの」という意味であった。将来の希望といった意味をもつようになったのは近代以降のことである。「夢」「願い」どちらにしても、叶うときというのは自分一人だけの力ではなく周りのサポートなどが必ずと言っていいほど存在する(少なくとも自分自身の場合)。相手の願いがかなった時は、相手の努力をねぎらい感謝し、自分の願いがかなった時は周囲の努力やサポートに感謝したいものである。
2016/01/22 13:59
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
客観的視点
短歌や俳句の解釈は難しく、小中学生ともに四苦八苦する単元。人それぞれ個性があるように、短歌や俳句にも顕著に個性が表れるもの。そんなわけで、作者のバックグラウンドについて知っておいた方が解釈しやすいので、折に触れて作者についての紹介や、作風などについて授業で紹介している。先日、良寛(お坊さん。子供と遊ぶのが好きで、世の中の俗事にはこだわらず、お坊さんでありながらお寺に住まず、毎日托鉢して、村の子供たちと遊び、詩や和歌や俳句を作ったり書をかいたりその日その日を悠々と過ごしていたと伝わっている。)について資料を作成し、生徒に渡したところ・・・・、「先生、昔のお坊さんって暇なの?!近所の子供たちを集めて遊ぶって・・・今の時代では考えられないよね。下手すると誘拐犯と間違えられるしね。」というコメント。成程、年配の世代では「良寛さん」というと「手毬」「世俗に染まらないお坊さん」と習ってきて、そのイメージが固定化されているが、別の視点で見ると先のような発想になるんだと新鮮であった。生徒の発言が適切か不適切か云々ではなく、言われたことをそのまま受け入れるだけではなく自分なりに考え、疑問点を持ったり冷静に考えるという姿勢に対して素晴らしいと思うのである。客観的視点を持ち続けられるよう意識したいもの。生徒から学ばせてもらう有難い日常である。
2016/01/21 11:43
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
読み手との会話
魅力的な文章、読みたくなるような文章には共通点がある。それは「次々に先を読みたくなる文章、言い変えると読み手の期待に応えてくれる文、読み手と対話が成立する文章」と言える。単純に文が箇条書きのように並んでおり、別々の内容がバラバラに書いてあったとしたら…読み手はもう投げ出してしまう(←ビジネス文書ではなく、あくまで長文としての読み物の場合)。文と文の間には、読み手から予想される質問が隠れている。(例)メロスは激怒した。(え?いきなり何を怒ってるの?)かならず、かの邪智暴虐の王をのぞかなければならぬと決意した。(え?メロスって一体何者?)メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き、羊と遊んで暮らしていた。けれども邪悪に対しては、人一倍に敏感であった。(成程そういうことなんだ・・・。それにしても王様が何をしたのだろう?)※本文は太宰治著「走れメロス」より、( )は想定されるであろう読み手の質問。思い起こしてほしい。本屋さんや図書館で本を手に取ったときに、当然全頁を読めるわけではなくパラパラと何ページか拾い読みをして、続きを読みたいと思った時にそれを買ったり借りたりする。本を手に取って選ぶことこそが、実際に本屋さんや図書館で本を手に入れる楽しみ。さて、逆に言うと自分の文章を読み手に飽きられないためには・・・「もっと読みたい」と思わせるような文章を書くことが大切になってくる。
2016/01/20 12:38
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です