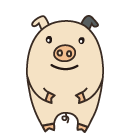小さな国語塾のつぶやき
理由付け
先日、相手を納得させるためには「理由」「根拠」を明確にすること!と書いたが・・・。正直に言うと、自分自身は昔から「理屈」よりも「直感」で物事を勧めるタイプで「~だから」ではなくピンときたら決めることが多い。(むろん失敗することも多々ある!)そして必要に応じて後から理由付けすることもしばしば・・・・(苦笑)。長年来の友人はそのことをよく知っているので、「結論」を言った後に必死で「理由」を演説する様子を見て「大丈夫、結論だけで説得力あるから」と言ってくれ、ありがたい限り(単に迫力があるから説得力が増すだけか?)。まあ、人間に備わった本能や感情がなせるわざで、理由なくして「こうだ」と思うことは誰しもあること。必要に応じて理由を考え、ましてや相手を説得させなくてはならない時には論理づける。ところで、人間は往々にして「出来ない」「しない」ための理由付けを必死で考えてしまいがち。例えば「部活が忙しくて、勉強ができなかった」「他の科目を勉強していたので国語が出来なかった」などなど。でも折角ならば「出来る」「する」ための理由を後付けでいいので考えた方が建設的。「部活で忙しくて長時間の勉強は無理だが、15分ぐらいならば漢字を学習できそうだ。」等。自戒を込めて。
2016/02/08 10:12
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
ストレス解消
早いもので、もう2月・・・・旧暦でも2月8日(月)に新年を迎え、新しい年の始まりとなる。言い変えると、中学三年生は受験シーズン本番を迎え、他学年も後期期末試験をひかえており、中学生は皆ピリピリと緊張している時期(真面目に勉強している子は)。さて、特に受験生にとっては高校受験の合否の結果によって将来が大きく左右される?!と緊張の度合いも尋常ではない。緊張してしまうのは仕方ないのだが、当日に本来の実力を発揮できるようにするためにはストレス解消、リラックスする工夫をした方がよい。それには①新しい問題集には手を出さない、過去問を解くことや苦手分野克服を心がける②ケアレスミスをなくすためにはどうしたらよいかを実践する(何を問われているかをチェックする、計算式では必ず見直しをすることを徹底するなど)。③モヤモヤした気持ちを誰かに聞いてもらったり、身体を動かすなどしてリフレッシュする。特に③が意外と重要だと思う。なぜなら、メンタル部分が弱ると身体へも影響を及ぼし、その結果悪循環に陥るから。とはいえ、モヤモヤした気持ちを聞いてもらったり、身体を動かすチャンスがないという場合は「書く」ことがお勧め。人に見せる時は内容を考えた方がいいが、自分だけ!という場合はどんな内容でもどんな筆跡でもOK。ぜひお試しを。ちなみに、自身はこうしてブログを書くことによって、かなりのストレス解消をさせてもらっており(※読む人によっては「あ、あのことだ・・・」と分かるような内容になっていることが多いブログ内容!苦笑)。書くことがメンタル部分の健康にいいことは実証済み。
2016/02/07 14:17
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
慣らふ
先日、小説における「前文」は重要!と生徒たちにはもちろんのこと、ここのブログでも紹介した。今週はいかに小説の「前文」が大切か?を実践しようと小説の問いを扱ったプリントを準備して授業に臨んだところ・・・・。生徒から何気に渡された、先日の学力テストの問題を見て愕然とした。というのが、中学2年生の学力テスト内の古文の問題では、抜出しの問題の答えとして前文から抜き出すというものがあった。現代文に限らず、ましてや古文では皆「前文」は軽く読んでスルーしてしまいがちで・・・。思わず「しまった!古文でも前文はしっかり読むように伝えておけばよかった」と思ったのだが後の祭り。とはいえ、ある意味、現代文に限らず古文でも「前文は重要」と実感しただろうから、次回からは前文を意識してくれることを期待している。聞いただけではなく、やはり何回か演習や経験を伴わないとなかなか実感はわかないもの。まさに「習うより慣れろ」的な要素が強くなってくる。ちなみに「習う」の語源は「倣う(模倣、真似する)」だと以前のブログで紹介したが、実は古文で「ならふ」は「慣らふ」と書く。まさに倣うことと慣れることが両方大切だということか。
2016/02/06 14:57
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
自己主張
昨日はうっかりしており、書いたブログを公開するのを忘れていた~!今日は気を取り直して、張り切ってブログを書いている。さて、昨日の小学生高学年のクラスでは「小論文」とはどういったものか?を簡単に説明し練習した。結論を言うと小論文とは「イエス、ノー」をはっきりさせ、さらにはその根拠をしっかりと述べることが大切な文章。昨日のお題は「夏休みに宿題を出す方がいいか?出さない方がいいか?」への意見をはっきりさせ、その理由を述べるという練習。ただし「宿題をするのがめんどうだから、遊びたいから宿題は出さない方がいい」という意見は説得力に欠けるのでタブーという条件付き。かなり苦戦しながらもそれなりに理由を考え着いた彼らは見事だった!さて、年齢を重ねて経験豊かになっていくとどうしても自己主張を相手に押し付けがち。しかも自己主張への理由が「長年の経験から・・・・」というぼんやりとしたオブラートで包んだような理由でおしまい!というパターンに陥りがち。それに気がつけば、理不尽な自己主張を相手から押し付けられても冷静に対処でき、逆に自分が自己主張するときはきちんとした根拠(理由)を述べることが出来る。侮ること勿れ国語力!
2016/02/05 12:22
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
基本的なテクニック
昨日、授業終了後に保護者の方から「学校の国語授業はよく分からない→だから面白くないとなってしまいがちだけど、国語塾で教わったように解いてみると『あれ?こんなに簡単に解けるようになった』⇒『だから楽しい!』となるんですよね~!誰も今までこんな風に教えてはくれなかったのです・・・」という有難いお言葉を頂戴した。「学校と同じ教え方をすることは塾としての存在価値がない、いかに分かりやすく、ここに来てよかったと思ってもらえるか?」と常日頃から教え方などなど研究している立場としては本当に嬉しい言葉であった。誤解のないように申し上げておくが、決して学校のことを批判しているわけではない!学校と塾の役割が違うと捉えているのである。現在の学校教育は、個性を大切にするという名目の元、型どおりに考えることを否定する傾向がある。絵も読書感想文も作文も「思った通りに書け」「好きなように書け」というばかりで、テクニックも論理も教えないというパターンが多いと感じる。でも、自主性を持たせるため、自分で考える力をつけるためには、まずは押し付ける必要があると思う。基本的な考え方のテクニックを示し、それを見よう見まねで繰り返させ訓練する必要がある。小学校低学年で足し算、引き算、掛け算、割り算を徹底的に練習、暗記させたからこそ複雑な計算が出来るようになるのである。それと同じことが国語でも言えるのではないか?まずは最低限の基本的な決まり、型を身につけることが大切。(これは2月4日に書いた文章だが、うっかりしてアップするのを忘れており・・・決して体調を壊したりしたわけではないのご了承を。)
2016/02/05 00:17
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
文章の癖
人には必ずあらゆる癖(個性)があり、当然文章にもそれが表れ、その文体によって「この作家好き!」「苦手」とファン層が分かれるわけである。が、多くの人に読んで理解してほしいという場合は書き方に「読みやすい文章を」という工夫が必要。さて、最近「アンドロイドは人間になれるか」(石黒浩著)という本を興味深く読んでいるのだが・・・正直言って読みやすいなあと思っていたところ、やはりと言うべきか?この本の文章そのものは石黒氏ご本人が書いたわけではなく、氏が「これまでに書いた文章と、新たに語った話をライターの飯田一史氏に書き起こしてもらい、話を分かりやすく楽しく構成してもらった。(中断)全てを正確に記述することが、必ずしも正確に物事伝えることにならないと考えたからである」とのこと。さすがに中高生が別の人に書いてもらうことはタブーだが、①果たして自分の書いた文章が分かりやすいか、相手に意図が伝わるかを確認してもらうこと。②多少の誇張はあっても嘘のない範囲の誇張ならば、使ってみる、という工夫が有効。また、大人の場合だとなかなか添削してもらうチャンスは少ないのだが、友人同士のメールやり取りなどで敢えて別人格のような口調で文章を書いてみるとお互いに新たな発見があったりするもの。※石黒氏はマツコ・デラックスさんを忠実に再現したアンドロイド「マツコロイド」を監修した人物。石黒氏は知らなくても、マツコロイドは意外と知っている人が多いかも。去年末には札幌のPR大使としてマツコロイドが就任。
2016/02/03 13:44
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
塾選び
昨日の午後7時過ぎに、用事があって芽室駅周辺を車で運転していると…多くの中学生たちが親の送迎であちこちの塾への入っていくのが見え、改めて駅周辺に学習塾が乱立していることに気づいた。皆それぞれ自分に合った塾!と思って頑張ってるといいなあと思いながら見ていた。さて、職業柄か?今も昔も「国語以外の塾を探していますが、どこがいいか知りませんか?」という相談を受けることが多い。結局、どの方にもお答えするのが次のこと。①周りの評判や口コミも大事だが、何よりも塾選びの基本は、自分の目で見ること。②どんなタイプの塾に通うべきかを決めること。この2点が塾選びの中でもっとも大切なポイントだと思う。というのは塾には、進学塾・進学予備校、総合塾、補習塾があり、それぞれに大人数一斉指導、少人数制指導、個別指導と分けられる。また、宿題やテストの有無、面倒見の良さなどなど言いだしたらきりがない。また、親にとって都合のいい塾(宿題が多くて、面倒見が良くて、学校より先に進んで・・・)が必ずしも本人に取って良いとは限らない(本人は宿題が苦痛で仕方ないという可能性も出てくる)。さらには通塾可能かどうかという条件も出てくる。つまり親子共にベストの塾というのは少なく、8割ぐらい条件を満たしていればOKという気持ちでいることが大切か。逆に言うと、国語塾に来てくれている途中で「あ、ちょっと違う・・・」という場合は遠慮なく別のところに移ってもらうことをお勧めするし、逆に別の塾から国語塾へという場合、共に大歓迎。
2016/02/02 13:53
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
作者の意図
最近、仕事に関する夢ばかりをみている。とはいえ、悪夢ではなく漠然と「仕事の夢だった」と覚えている程度なのであまり神経質になったり「夢判断」「夢分析」をしようとは全く思っていない。逆に「夢の中でも仕事をしているなんて、自分は偉い!」と思っている(笑)。さて、最近寝る前に「夢十夜を十夜で」(高山宏著)を読んでいるから、夢について起きた時にひっかかるのかなとも。さて、先の「夢十夜・・・」は夏目漱石の「夢十夜」を大学の講義で学生とともに読み解くという授業を、本で監修したものである。以前は何気なく普通に?神秘的だなあと思っていた「夢十夜」のストーリーをああだこうだと分析している内容で、「へー!こういう解釈もあるんだ」と思う反面、どういう意図、テーマで書いたかは本人にしか分からない。しかも解釈はそれぞれ自由なであり、自由に解釈してほしいというのが作者の意図そのもの・・・と元も子もないことを思ってしまう。自分自身に関して言えば、日ごろ仕事で作者の意図を推理しているのでオフの時ぐらいは自由に作品を楽しみたいもの。今日から違う本を読むべくして別の本をゲットしようと張り切っている。
2016/02/01 09:54
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
「聴き取り」の目的
当塾では様々な形態の「聴きとり」を実施している。時には「この人の声怖い!滑舌悪い~」と生徒からブーイングを飛ばされながらも(苦笑)、敢えていろんなパターンの物をチョイスしている。その中の一つとして興味深いのが、昨日の三段論法的な内容のヒアリング。例えば、「猫はネズミよりも小さく、猫は象よりも大きい。さて、一番小さい動物は?」といった内容のもの。「象<猫<ネズミ」なので答えは「象」。この問題の素晴らしいところが①文章を図や記号で表す訓練になる②三段論法の基礎となる概念を養う③自分の常識や思い込みを外し、きちんと内容を把握する、という3点の訓練になるという点。常識で考えればこの放送の内容は明らかにおかしいのだが、内容云々はともかくとして、正確に相手の言うことを聴きとるかが大切。聴き取りに限らず、文章を読むときもついつい自分の基準で読んでしまいがちだが、そうすると正しい答えにはたどり着かない。客観的に・・・とどんなに意識をしても必ず自分の個性が表れてしまうもの。それはそれで致し方なく、特に芸術においてはそれが才能と言える物になることもある。が、まずは「素直」に受け入れるという姿勢が何事にも大切で、その感覚を「聴きとり」を通して自然に身につけていってほしいと願うのである。
2016/01/31 14:39
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
三段論法
論理的な文章の代表的な論法に「三段論法」がある。二つの前提から一つの結論を推論する方法で①大前提②小前提③推論という順番をとる。例えば、①『鳥は卵を産む』②『ペンギンは鳥』③『だからペンギンは卵を産む』と言った具合に使う。ここで、①『ペンギンは空を飛べない』②『ペンギンは鳥』③『だから鳥は空を飛べない』としてしまうと「あれ?なんだかおかしい」となる・・・。つまり何が重要かというと一番目には必ず大前提、次に小前提という順番を守ること。文章で書くとなんだか難しく感じるが・・・、この考え方を覚えて実践していくと説得力のある文を書くことが出来る。さらには、生きていく上で行き詰った時に冷静に判断をすることが出来るようになる。例えば何か大きな失敗をしたとするとつい自分を全否定してしまい①「自分は大きな失敗をして周囲に迷惑をかけた」②「周囲の人は皆、自分を嫌っているに違いない」③「だから自分は価値のない人間だ」とマイナス思考になりがち。でも逆に①『周囲に迷惑をかけない人間はいない』②『私は人間』③『だから周囲に迷惑をかけてしまうこともある』と考えていくと決して自分の犯したミスや失敗と言うのは特別ではないことが分かる。また①『すべての人間に好かれる人間はいない』②『私は人間』③『私のことを嫌う人間がいてもそれは特別なことではない』と考えると気分が楽になる。むろん、都合よく自分以外の人やモノに責任転嫁するのは言語道断だが。
2016/01/30 03:12
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です