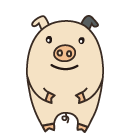小さな国語塾のつぶやき
詩の鑑賞
「詩」と聞いて何を感じるだろうか?「素敵!」「大好き」というタイプがいる反面、「何を書いているか分からない」「キライ」というタイプも同じぐらいの割合でいるだろう。説明文などは大半の小中学生にとっては「難問」だろうが、「詩」は見事に好き嫌いが二極化する。短い文章なので読みやすいという利点があるが、なにぶん作者の主観のオンパレードなので何を言っているか分からないという事態に。ではどうするか?①表現技法を覚える②何が何に例えられているかを把握の2点に尽きる。ただ、②に関しては「なぜ、○○が△△に例えられているのか理解できない」となると、やる気がなくなる。とりあえず学校の定期試験に関しては、暗記するのが一番の近道。とはいえ、人間は納得しないことはなかなか覚えられない。その場合は、ノートなどに「自分は『蝶の抑揚』は手をふって挨拶しているように感じるが、作者はそれを『信号』に例えている」といったようにメモをして整理する。そうすることによって、自分の考えと作者の考えがきちんと整理され、覚えやすくなる。また、対比して文章を書くという練習にもなる。要するに頭ごなしに覚えようとするよりも、整理整頓して冷静に?覚える工夫を。
2016/02/18 14:30
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
教えを乞う姿勢
「ものぐさ太郎」「三年寝太郎」などといったおとぎ話、昔話が日本で伝承されている。共に、いわゆる「ニート」の若者が、あることがきっかけで幸せになるといった話で、確かに現代でも「ニート」だったけれど今は大成功しているという人はいる。が、そういうタイプの人はもともと内に秘めたる才能があり、それを熟成する時期必要であり、しかるべき時期に開花したと言えるだろう。元々の蓄積がない状態では「棚からぼたもち」なんていう幸運なことはまず起きないと思った方がいい。まれに「国語の勉強法を教えて下さい!」と教科書だけを持参して質問してくる中学生がいる。(※現在、国語塾に在籍している生徒さんにはそんな非常識なタイプは誰一人いないことをここに明記しておく!)よくよく話を聞くと、学校で配布されたワークやプリント類を一問も解いていない。ただ、何度も何度も教科書を読んでいるのである。むろん、教科書を読み込むことは大切だが文字を追っているだけではどこが重要なのかは分からない。内容をきちんと理解しているかどうか確認のために演習をするのであって、その演習をせずに「国語が苦手です。勉強法は?」と聞かれても・・・・。まるで「引きこもり、SNSなどとも無縁」な状態で「出会いがないんです!モテないんです」と言っているのと同じ。自力では最初は正解に行きつかないことが多いだろう、その時に「なぜこの答えになるのですか?」と質問されるのは大歓迎である。教えを乞う姿勢というのも大切なことの一つだなあと思う今日この頃。
2016/02/17 13:44
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
不測の事態
1月に行われた英検、無事にクリアしたと報告してくれたMちゃん。実は日中に消しゴムをなくしてしまい(後で理科ノートに挟まっていたことが判明)、放課後に受けた英検では消しゴムなしで臨んだという・・・恐ろしや・・・。そんなわけで、合格の報告を受けてホッとしている。英検ならば何度でも挑戦できるが、入試はそうはいかない。受験勉強のみならず「不測の事態」に備えることも大切!今日は十勝管内では私立の一般入試が行われている。昨日、今日の試験に備えて会場の下見をしてきたというNちゃん。今日は天候にも恵まれ、無事に今頃試験を受けている頃だろう。人生がかかっている?入試では「不測の事態」に備えて①消しゴムや筆記具は多目に準備して持参②学校の連絡先を把握しておくこと③当日までに下見をしておく、ルートを確認④余裕をもって家を出るなどなど、この4点ぐらいはちょっとした心がけで誰でも実行できる。それ以外にも・体調管理・メンタル部分強化?!などなど工夫するに越したことはない。さて、最近は自分が経験した失敗を元に開発したという触れ込みで、受験までにしておくべきこととして「呼吸法、リラックス法」といった教材が売られているようだ。中身を見たことがないので何とも言えないが、失敗を商売や仕事に生かしている彼らにとっては昔の失敗はもはや失敗ではなくなってるが、それは自身の努力の賜物。半数以上の人は失敗を失敗のままで終わらせてしまうに違いない。少なくとも防げる失敗、不測の事態は避けたいもの。
2016/02/16 13:19
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
シンプルな方法こそ・・・
中学3年生にとっては先週の公立の推薦入試に続き、今週は私立の一般入試、そして3月上旬には公立の一般入試・・・。この時期になると大抵の人が「後悔の連続」の時期を迎える。「ああ、もっと中学1,2年生のうちからきちんと勉強しておけばよかった・・・」などなど。そして「よし、高校生なったら生まれ変わって頑張るぞ~」となるのだが、なかなか・・・(苦笑)。ではいわゆる「後悔しない?」方法とは。少なくとも中学生のうちは「与えられたことをする」に尽きると思う。それは・学校・塾・家庭教師から与えられたカリキュラムを素直にこなすこと。学校は30人近くを対象に授業をすすめ、課題を出すためどうしても自分には合わない、あるいは先生によっては宿題がないという場合があるが、塾や家庭教師では大抵レベルに応じての課題があるはず。とにかく素直にそれを「こなすこと」が実は勉強において一番の近道だろう。そんな当たり前のこと?と思われるようなシンプルな方法こそが一番の近道だということは長年の経験から断言できる。むろん、与えられた課題だけでは物足りない~という場合は自主的にどんどん進めるのは大賛成。
2016/02/15 14:43
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
人の不幸は・・・
「人の不幸は蜜の味」をいう慣用句があるが、果たして本当か?最近はかなり研究が進み、どうやら先の慣用句は正しいであろうことが実証されつつある。そのうちの、一つを紹介。「なぜ人間が人の不幸の話が好きで、その話を聞いた時に団結が強まったような気がするのかというと、必ずしも人の不幸を喜ぶというのではありません。脳科学的には、人生なにが起こるのかわからないので、いろいろな事例をあらかじめ頭の中でシュミレーションしておきたいということです。」(「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本 〈茂木健一郎 羽生善治〉P66から抜粋)成程、確かに順風満帆の人の話題はあまり興味を持つことはない。そういう話を聞いたとしても「へ~、そうなんだね。」で終わる。人の不幸を話を聞くと「同情、共感、優越感」などを無意識のうちに持つというのが人間の性。が、同時に嫌な気分になるというのも事実。「もしも自分もそんな風になってしまったらどうしよう・・・」などと感じる。正直言って、自分自身としては「不幸だったけれど、何らかのきっかけで幸福になりました」という「元不幸」の話がが一番参考になり、そういう話を聞くとホッとする。塾を主宰している立場としても「最初は底辺だったけれど、こ○○がきっかけで成績が急上昇した」となってくれないと困る~。「人の不幸は蜜の味」よりも「人の元不幸は蜜の味」を理想としている今日この頃。
2016/02/14 06:54
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
理解出来たような気分
成績が伸び悩む、あるいは降下し続ける…という場合の対処法としては①環境を替える②勉強の方法を替えるの二点に尽きる。とはいえ、勉強の方法が分からない、うまくいかないから成績が思わしくないのであって「勉強の方法を替えろ」と言われたところで「ハイそうですね」とはいかない。となると、まずは①を試みるのがベターか。環境を替えることによって自分に合った勉強法を教えてくれる指導者に出会えるかもしれない。また、勉強せざるを得ないような環境になるかもしれず、そうなるとしめたもの。が、が、ここで気を付けなくてはいけないことがある。予備校や塾の講師というのは指導力が高いことが多く(そうでないタイプは淘汰されてしまう・・・)、授業を聞くと、まるで魔法にかかったように「理解出来たような気分になる」のである。授業を受けた日は「分かった~!成程!」と意気揚々とするのだが、いざ自分で解いてみようとすると解けない、忘れたということが起りうる(経験者は語る!)。では、「理解出来たような気分」→「理解する」となるにはどうするか?「教わった方法で、とにかく自力で解いてみる」しかない。それでも解けない場合は講師に質問すればよいのである。学問に王道なし・・・結局は最終的には本人のやる気次第。
2016/02/13 03:11
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
八丁
「胸突き八丁 (むなつきはっちょう)」という言葉がある。意味は山頂付近の険しい登り道。転じて、物事を成し遂げるのに一番苦しい時期、正念場のたとえ。「胸突き」は、山や坂などのけわしく急なところで、もとは、富士山頂で、頂上まであと八丁(約872メートル)の最後の険しい登り道を言った。それが他の山についても用いられ、さらに転じて、物事の大詰めの一番苦しい局面の意で用いられるようになったもの。今日は公立高校の推薦入試。むろん、全員受かるわけではなく何人かが不合格となり、その場合は3月に一般入試を受けることになる。推薦を受けない中学3年生は一般入試の一発勝負に向けてまさに今が「胸突き八丁」の気分で頑張っている頃。泣いても笑ってもゴールは目前。体調管理をしっかりとして本番を迎えてほしい。さて、「八丁」のつく言葉と言えば「口も八丁手も八丁」という諺がある。この場合の「八丁」は、八つの道具を使いこなす程達者ということで物事に巧みなことを表し「八挺」とも書く。同じ字でもいろんな意味があるから面白い日本語。
2016/02/12 13:03
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
対比の内訳
国語においての三つの骨組みの一つが「対比」。文章を読むときはもちろんのこと、書く時も「対比」を意識するよう口酸っぱく指導しているが・・・。ただ、いきなり「対比」と言われても普通はピンとこない。「対比」は大きく分けて二つに分けられる。①同類のもの、複数を単純に比較する②一つの物事を別視点から見て論じるの二点。例えば①は「日本人の特性」を述べて強調するために「外国人の特性」を用いて比較する。つまり同類のものを比較するというやりかた。図式化するならば横軸と言った類になる。②は有名なオリンピック選手や、ある分野で秀でている人のことを述べる時、彼らの実績などを「光」とするならば、その光の陰に「たゆまぬ、信じられないぐらいの汗と努力がある」と言った具合に物事を別視点から、表裏で見る。横軸に対して縦軸と言える。もっと分かりやすい例を挙げるならば、自分自身と他人を比較するのが①、自分自身の過去と現在を比べてみて・・・「あの時の苦労があったから今の幸せがある」という考え方が②。いつも書いているように、一つの物事に偏るのはタブー。「対比」においても①②両方のをうまく操ることが出来ると、国語力がついている証拠。
2016/02/11 17:43
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
ありきたりのアドヴァイス
自分自身が主催している国語塾は本当に小さな小さな塾・・・というよりもお教室といった感じである。とはいえ「塾」として皆が快適に学習するための、最低限のルールは決めており、そのルールや方針については体験時に口頭で伝え、入会してくださる方々には書面でお渡ししている。とはいえ、杓子定規にどんな場合でもそのルールを順守しなくてはならないかというと、むろんそうではなく応相談でやっている。また、クラスや生徒さん個々人によってこちらからのアドヴァイス内容を変えている。だから、もしも隠しカメラでもあったならば・・・「あれ?先生はこの前と違うことを言っている?!」とチェックされるような場面もちらほら。「うちの子供は読解力がないのです。国語が嫌いで勉強しないんです」という相談に対して「とにかく本を読ませてください。問題集を一日15分でいいので解かせてください」とアドヴァイスしたとしてもそれは役に立たないだろうと思っている。また、そういった誰にでも思いつくような内容のアドヴァイスは相談者側としても、既に聞き飽きて、聞きたいとは思っていないだろう(昨日のブログとも関連するが)。そういったありきたりの情報は役に立たなかったから、国語塾に来てくださってるわけだから。当国語塾は、そういった細かいフォローを出来るのが大手塾産業や通信教育にはない強みだと自負している。ぜひ新年度から国語塾に行ってみようかという方、大歓迎!
2016/02/10 13:35
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
紙面上の身の上相談
雑誌や新聞紙上で「お悩み相談室」といったコーナーをよく見かける。相談内容によって回答者は様々な分野の専門家で構成されている。それらを読むたびに「さすがだなあ」と感心する。①決して相談者のことを全面否定しない②相談内容自体をも全面否定せずに、あくまで客観的に見ている③時にはギャグを入れながら、バランスの取れた折衷案を提案している。この3点がきちんと守られている回答を読むと本当に勉強になる。むろんケースバイケースだが、相手を説得させることは大切だが100パーセント片方だけが正しいということは稀である。ある雑誌での、僧侶(作家としても活躍)小池龍之介氏の相談回答。相談者「時間や締め切りに対して厳しく、自分自身は必ず約束の10分以上前に目的地に到着するが、友人はいわゆる遅刻魔で必ず10分以上遅れてくる。その結果20分以上待たされることになりイライラする。かといって自分自身がジャストの時間に目的地に行くことや、ましてや遅刻することはポリシーとして有り得ない」小池氏「(前略)待ち合わせ場所をおしゃれなカフェなどにし、相手を待っている間を自分の時間として読書などをして楽しんではどうか?そうすることによって双方ともにストレスがたまらない・・・」。国語の評論などを読んでみると分かるように、優秀な作者は主張をしつつも必ずしも他の考えを排除しているわけではないことに気づく。素晴らしい文章などから学ぶことは多い。
2016/02/09 13:24
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です