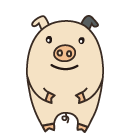小さな国語塾のつぶやき
解説本
「夏目漱石、読んじゃえば?(14歳の世渡り術)河出書房新社 (2015/4/22)」が面白い!ぜひぜひ、お勧めである。これを読んだ後に夏目漱石の作品を読むと理解が深まるのみならず、楽しく読めることだろう。さて、「本を読むことによって多角的視点が養われる、教養が身につく。だから読書しなさい・・・」と小中学生の頃には誰もが大人たちに言われたことだろう。さらには、大人たちがさす「読書」とは「名作」「伝記物」をさすのであって、いわゆるライトノベルスやアニメが小説化されたものを指すわけではないことは誰もが暗黙の了解で分かっている。とはいえ昔からの「名作」となると正直言って敷居が高い、つまり面白くない、読むのが辛いのである。なんとか頑張って読んだとしても「一体何が言いたかったの?」「わけわかんない」となるのがオチ。そんな場合に役立つのが先のような解説本!昔はいわゆる解説本は世の中になかったのだが、最近は様々の解説本が出版されておりしかも中身が面白いのである。いきなり名作・・・は厳しい場合はたとえ邪道と言われようがなんだろうが、解説本などを先読みすることをお勧めする。ぜひお試しを。
2016/02/28 14:55
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
長所・・・
文章を書くのが上手な中学二年生のS君。さらなるスキルアップを!と思い、数ある「型」のうち難易度の高いものを紹介、10分で200字書くという課題を出した。テーマを何にするかを迷っていたので「自分の長所を一つ上げて、それについて書くこと」と指示したのだが「自分には長所がないから・・・」と却下された。その後、自分なりにテーマを見つけて書き始めたので、「じゃあ代わりにS君の長所について、この型に当てはめて文章を作るよ」と声掛けをして作業を開始したところ「さすが、国語の先生!さらさらと書いてますね」という嬉しいコメント。「そりゃあ、これが仕事だしS君は長所が沢山あるから書きやすいんだよ」と書きながら返答。立場上、書けて当たり前、書けないとなるとかなりの問題あり・・・なので意外なことを褒められて思わず嬉しかった。と同時に実はこの「素直さ」と「謙虚さ」こそがS君の長所だと前々から思っていたので、そのことを文章に表してみたのだ。書きあがった文章をS君に見せ、差し上げると照れながらも喜んでくれた。長所がない生徒はいない(少なくとも自分が担当する生徒さんは)!素直で謙虚なタイプは知識の吸収や成長が早いという信念はこれまでもこれからも変わらない。
2016/02/27 04:04
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
国語力は必須
「人間性を問われる職業こそ、国語力が必要」ということを強調して話されたIさん。昨日、Iさんは用事があってお教室にお見えになり、元々の用件については30分だけ、その後は全く関係のない話で延々と盛り上がったのだが・・・。その会話の中で何度も何度も強調されたセリフが先の内容。実はIさんは4月から看護学校に入学予定で、そのために必死で看護師受験専門の学校で勉強されていた(ちなみにIさんはご主人、子供さん二人という家族構成)。ご自分が今から入学される学校ではとにかく「国語力」が重視され、徹底的に仕込まれるとのこと。看護師さん=医療関係=看護の知識と思いがちだが、確かに考えみれば知識さえあればいいというものではない。自身に何らかの不調を抱えて心身ともに弱ってるであろう患者さんの相手、同僚同志で患者さんの引継ぎを行うためのカルテや書類記入などなど、知識+コミュニケーション能力が必要な職業の代表的なものだと納得。幸いにして健康体の自身は病院、看護師さんにお世話になるというチャンスがほとんどない。が、逆に言うとたまーにお世話になるであろう時にまともに日本語を話せない?!看護師さんがいたら・・・と思うとぞっとする。反対に、教養を身につけている素敵な看護師さんに巡り合えると身体の不調なんてあっという間に飛んでいきそうなもの。どんな職業でも「正しい日本語表記」「分かりやすい文章(主語と述語がしっかりしている)など」は必須!そういうことに気づく人が増えてくれると嬉しいなあと思う今日この頃。
2016/02/26 13:22
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
拝
名前を呼ばれると「ハイ」と元気よく返事をしましょう~と言うようなことを幼いころから教えられるし、返事する側もされる側も元気よく「ハイ」という声が聞こえると気持ちがいいもの。さて、この返事の「はい」の由来は「拝」だと本で読んだことがある。名前を呼ばれたことに対する感謝の意味から来ているとのこと。「ハイ」には、自分のことを気にかけて下さり、そして呼んでくださりありがとうという気持ちがこもってると思うと気持ちがいいもの。そんなことを日ごろ考えて返事するわけではないが、例えば「おい」「ちょっと」と呼ばれるよりも「○○ちゃん」「△△さん」と名前を呼ばれると気が引き締まるのは事実。また、以前に書いたが古文では言葉には魂がこもっているためむやみには大切な「名前」を読んだり書いたりしない、ということも納得。それだけ名前って大切であり、「名前を言う」→「名言」となる。色々と由来や意味をつなげ合わせると楽しいもの。
2016/02/25 17:06
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
伏線
長年生きていると・・・皆色々と思うことがある。しかもその内容というのが同世代ではほぼ一致するのが興味深い。昨日、友人から「ありの~ままの~♪(中断)もがくことなど致しません。釈迦の手の上の孫悟空・・・」というメールが。今日は某知人と電話で話していると「人にはそれぞれ役目というのがあるんだと思う。だからどんなに自分の力で頑張ってるつもりでも実は既に決められていたのかと思うことがある。だからと言ってじゃあ何もせずにぼけっとしていればいいというのではなく、目の前にことを1つ1つ努力してやっていくことが素晴らしい人生への近道だと感じる。」という発言が。おおっ、皆悟ってる~~~~と感心するやら納得するやら。自分自身としては人生はまさに「小説」だと思う。優れた小説とは見事なまでに伏線が張られており、ちょっとしたエピソードがすべて結末につながるように計算されている。つまり見事な伏線があるからこそ、引き込まれる優れた小説だと認識される。まさに「事実は小説より奇なり」だとつくづく思うと同時に皆に感動を与えるような「小説」を実生活で刻んでいきたいもの。
2016/02/24 13:21
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
有終の美
兵庫県にある、お気に入りのオーガニックスーパーが来月で閉店するという連絡をもらった。HPを拝見したところ、きちん閉店に至るまでの思いや理由が書かれており「今が一番ベストの時期」と納得するのだが、それでもショックは大きい。と同時に「有終の美を飾る」という言葉がふと頭に浮かんだ。「有終」をうっかり「優秀」と書いてしまいがちだが要注意。意味は「最期まで成し遂げ、立派な成果を出して終わりを締めくくる」である。さて、先日、ある男子生徒に「将来は何になりたいの?夢は?」と聞いたところ「ウーン・・・・」としばらく沈黙。彼はハッと思いついたように「そうだ!将来は『めむろ国語専門塾』を継いであげる!あ、でも国語は苦手だから『めむろ数学専門塾』を開こうかなあ」という嬉しいコメント。思わず嬉し泣きしそうになったが・・・まだまだ現役で頑張るつもりだし、彼はとっても優秀(有終ではないので要注意)で、小さな小さな塾を切り盛りすることよりももっともっとビッグに羽ばたくはず!日本の将来を担う青年たちの生涯のほんの一時、一緒に学ぶことが出来るのは最高の幸せであり、○十年後には彼らに「有終の美を飾ったね」と言われるよう日々精進。
2016/02/23 03:06
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
関連
漢字は様々な読み方があったり、似たものが多く覚えるまでがとっても厄介なもの。特に人の名前は今も昔も「読めない!書けない!」という場合がしばしば。※一時のキラキラネームは最近なりを潜めて、いわゆる読みやすい名前が復活しつつあるそうだが。さて、定期試験の時期になると生徒たちの間で試験の話が飛び交っており、ついついお節介乍ら、耳ダンボにしている今日この頃。「皆、頑張ってるなあ~」と思うと同時に「漢字大丈夫?書ける?」と思わず突っ込みたくなっている。そんなわけで、特にに歴史では漢字を間違って覚えてしまうことが多いので、時々国語授業の最初か最後の5分で漢字の紹介をしようかなあと思う今日この頃。例えば、建武の新政を行った「後醍醐天皇」の「醍醐」とは元々は仏教用語で「最上」という意味で、実は醍醐天皇の醍醐は御陵のあった場所の地名に因んだものだったとか。そしてこの御陵の管理をしていた醍醐寺の名前の由来はというと、醍醐寺の湧水を飲んだ醍醐山の神の化身である老人が「ああ醍醐味なるかな」と言ったからだという説がある。そこから最上の味を「醍醐味」となったらしい。諸説は色々あるが、とにもかくも「後醍醐天皇」→「醍醐味(とても美味しい!)」をセットで紹介し、少しでも語彙や漢字の記憶を増やしていってもらおうと計画中。
2016/02/22 14:52
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
苦しさ半分、喜び倍の方法とは?
趣味のネットサーフィンで興味深いブログ内容を見つけたので紹介する。さらには、辛口コメントも続く・・・。「頑張る時や壁にぶつかったときの苦しさを半分以下に、成功した時の喜びを倍以上にするシンプルな方法を紹介します。その方法とは…仲間・先生と一緒に頑張ること、です。」(上田真司氏ブログより抜粋)成程、人間は孤独だとやる気が失せ、頑張りに伴奏してくれる相手がいると心強いのは納得。が、ここで気を付けなくてはいけないのは「相手に依存しすぎないこと」「ふさわしい相手を選ぶこと」、逆に人様から「ふさわしい相手として選ばれるようになること」という絶対条件がつくと思う。相手を選び間違うと共倒れになる危険性があり、しかも自分が素直に相手と一緒に向上するという意識を持たない限り、置いていかれるのがオチ。その点、国語塾に通って来てくれている某中学の同級生たち。お互いに切磋琢磨し、全員が自主的に宿題以上のことをこなしてくる。テスト前には同じ内容のプリント類を演習、友人が理解できている部分を自分が理解できていないと分かると必死で追いつこうと食い下がる姿には頭が下がる。そういう彼らを見ているとこちらも指導に熱が入り。。。。彼らを疲れさせている(苦笑)。もし万が一逆のパターン(依存心が強く、塾に通ってるから大丈夫的な態度で授業に臨むなど)の生徒がいたとしたら、おそらくこちらの指導熱も一気に冷めてしまい凍結間違いなし?!幸い、どのクラスでも毎回、指導熱は沸騰中。有難いことである。
2016/02/21 03:35
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
新分野
ほどほどのプレッシャーはプラスに働く?!とあらゆる筋の専門家が述べており、実際にその通りだなあと思うことは日常生活でもしばしばある。さて、去年の夏休みに中学生は学校の課題として「読書感想文」を5枚書くことになっており、皆本当によく頑張っていた。その姿を見て「生徒だけに書かせるのも・・・」と久々に自分も読書感想文なるものを書いてみたということは以前にブログでアップした通り。その後、折角だから・・・と地元の読書感想文コンクールに軽い気持ちで応募。が、が、が、立場上、ノミネートされて当然?!もしも万一のことがあったら・・・と自分一人で勝手にプレッシャーを感じていた。幸い、結果は「吉」と出たのでホッ。それにしても今回のプレッシャーはあまり健康的ではなかったかも?!来年度は仕事面において「新分野」への挑戦を考えており、それが実現すればよい意味でのプレッシャーを今以上に感じることになる。それが必ず自分自身への成長につながること間違なしだと確信している。新分野については諸所の事情から今はここでは明記できないが、必ず挑戦する予定で、それが実現したらブログで報告するのでこうご期待?!
2016/02/20 06:28
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
生徒自慢
将棋棋士の羽生善治氏は「プレッシャーのかかる状態に挑戦していくとか、緊張している状態に身を置くことによって、初めてその人が持っている能力とか才能とかセンスとかが、開花するということもあると感じています。」(「ほら、あれだよ、あれ」がなくなる本 P144より抜粋)と述べている。過度のプレッシャーや緊張は良くないが、かといってリラックスしすぎだと集中力に欠けてしまう、バランスが大事ということか。実は、昨日の高学年クラスでは前回に続き「小論文」についての授業計画を立てていた。が、なにぶん「小論文」というのは正直言って難しいので皆がついてきてくれるか?飽きないか?とかなりのプレッシャーを感じながら授業に臨んだ。ところが、授業前に手作りのきれいなキャンドルを見せてくれたS君。先日、イベントで作ったそうで、上手に出来たので見せようと持ってきてくれたのだ。別の生徒さん共々、美しい色のバランスなどなどをあちこちの角度から楽しませてもらった。おかげで、ほどほどに緊張しながらもリラックスしながらの授業開始。「食べ物の好き嫌いはなくした方がいいか?」というテーマについての賛否、理由、反論を和やかで、なおかつ真面目な内容をああだこうだといいながら検討。無事に原稿ノート1枚にまとめることが出来た。いつも場をほどよく和ませてくれるS君には感謝!!!
2016/02/20 06:11
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です