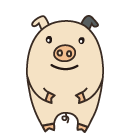小さな国語塾のつぶやき
ラジオ生中継
突然だが、今日の夕方5時40分ごろからFMウィングというラジオ番組で生中継されることになった。5時半まで小学生クラスの授業があるため、その後の放送。昨日の午後7時20分ごろに出演依頼の打診があり、急きょ生徒さん達にも連絡したところ、インタビュー等答えてもいいよ!という嬉しいコメント(むろん、名前などは伏せる予定)。ただただ、ありがたい限り・・・・。小さな小さな塾を紹介していただけること、お忙しい時間にも関わらず、授業終了後に残ってインタビュー等答えてくれる予定の生徒さん達の気持ちが嬉しく、感謝である。有難いなああと思いながらこのブログを書いてると、次の諺が頭に浮かんだ。「縁あれば千里」【縁があれば遠く離れた所の人と夫婦になったり、深い交際を結ぶようになったりするものだが、縁がなければすぐ近くにいても、口を利かないどころか出会うことさえなかったりするもの】。ネットで世界中とつながることが出来る昨今では、距離なんて関係なくなっており、ただ「ご縁があるかどうか」だなあとつくづく感じる。幸い、本当に素晴らしいご縁に恵まれて感謝の日々である。そう言えば、数か月後に本を出版予定の知人(本州在住)も突然一本の電話がかかってきて・・・本を出版することになったという。自分自身は「本の執筆」なんていう大それたことは考えたこともないが、「文章作成、添削、コラム執筆、大人の文章講座」等の依頼があれば大喜びで引き受けるので機会があればぜひご一報を。
2016/03/09 10:00
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
失敗談を参考に
吉田兼好が書いた徒然草 110段「双六の上手といひし人に」に次のようなことが書いてある。「双六の名人と呼ばれている人に、その必勝法を聞いてみたところ、『勝ちたいと思って打ってはいけない。負けてはならぬと思って打つのだ。どんな打ち方をしたら、たちまち負けてしまうかを予測し、その手は打たずに、たとえ一マスでも負けるのが遅くなるような手を使うのがよい』と答えた。」スペースの関係上、原文は省略し現代語訳のみを掲載。さて、作者(兼好法師)も述べているが、この考え方はあらゆる道に通ずると思う。例えば、入試の発表後に先輩たちの受験体験を聞く機会があると思うが、その時に「成功談」ではなく「失敗談」にこそ参考になるような貴重な情報があると心がけるべし。なぜなら、成功談は「××はやらなくていいよ」「△△は夏休み明けからでも十分間に合うよ」といった情報が混じりやすいから。この消去法的な考え方や体験談が後輩たちに必ずしも当てはまるとは限らないし、人間はつい無意識のうちに情報を自分に都合よく捻じ曲げてしまい「あ、△△は遅くからでも間に合う⇒今はやらなくてもいい」となってしまいがち。それよりも「□□をやっておくべきだった」という失敗談を貴重な情報として取り入れる方が勉強になる。どうしても「どうやったら受かるのか?」に意識がいき、成功談を聞きたくなるのだが発想を転換して「失敗しないためにはどうすればいいか」の重点を置くことの方が意外と大切か。
2016/03/08 12:06
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
共作
「小説の書き方」(須藤靖貴著 講談社発行)という小説がある。テクニック本ではなく、小説なのである。高校生3人が共作で小説誌の新人賞に応募する・・・・というあらすじなのだが、この小説を読むだけでかなり文章の勉強になる。そのうちの一つが「共作」。この小説内での共作とはリレー形式で文章を書いていくこと。一人で小説を書く場合だとプロット(全体の構成、あらすじ)を決めてから書き進むのだろうが、この場合はとりあえずトップバッターが原稿用紙10枚を書き、それを次に回す。原稿を受け取った人が、前の文章を読んで自由に構成を作り10枚書き次に回す、と言った具合。そうなると内容がバラバラになる?と思いきや、意外と斬新で一人では思いつかない展開になる。何よりも心が折れない。文章上達の秘訣は「まずは、書くこと」、つまり書き切ることが大切なので、時にはリレー形式を試してみるとどんどん筆が進み楽しい。ただしリレー形式をやってみるには「チームワーク」が大切。先日、国語が大好きで本当に頑張り屋さんのIちゃんのお母様から「宿題で出ている文章が進まないので、親がアイデアを出したり手伝ってもいいですか?」という主旨のご丁寧なメールをいただいた。手伝っていただいて問題ないといった主旨のメールを返信したのだが、手伝ってもいいという理由は先に書いた通り。「手伝う」というとなんだか罪悪感を覚えるかもしれないので、ぜひ「共作」!と思って親子で楽しく文章を作って欲しいと願っている。皆さんもご家族で、あるいは友人同士で共作をやってみてはいかがか?
2016/03/07 13:15
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
型やぶり
今までに何度も「文章の型」といったものが大切だと書いてきたが、小中学生にとっては「型」は面倒くさい決まり事となりがち。別に型を守らなくてもとりあえず文章を書くことは出来るから、どうしてもなかなか重要視されない。書いた文章が上手か下手かの判断は自分だけでは難しく、さらに言うならば好きなように文章を書いたとしても人に迷惑をかけないから。だが、これが人様にごちそうするお料理だとしたら?同じ材料を使っても、レシピ通りに作らずに適当にお料理すると…生煮え、味もいまいちという羽目になりかねない。最初は誰でも失敗はつきものだが、とにもかくも美味しいお料理を作ろうと思ったら、まずは素直にレシピ通りに作ってみる、それから自分の好みに合わせて調味料などを加減する。お料理だと食べた瞬間に美味しいまずいが一瞬にして判断できるので、一度失敗すると二度目からは真剣になる。声を大にして言いたい「料理法を習得することと文章上達の道のりは同じ」と。文章上達を目指すならば、真剣にまずは「型(レシピ)」を守り、良文に沢山触れて、それらを「真似る」こと。「型破り」というのはまずは「型」が完成して初めて出来ること。
2016/03/06 00:41
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
持ち時間
老人介護施設で働く職員が、「ライン」と呼ばれる分刻みの業務表へのストレスが高じてお年寄り3人を転落死させたという事件が川崎市であった。いくらストレスがあったからとはいえ、やっていいことと悪いことがあり、人の命を奪うことは言語道断。ただ、人を相手の仕事において「分刻み」にスケジュールを組むことは若干無理があるような気がしないでもない。むろんある程度の「目安」は大切だが・・・。かなり以前に「個別指導」を専門とする塾で教えたことがある。基本的に一人の生徒さんへの持ち時間が決まっており、曜日によりけりだが、持ち時間を守ろうとすると消化不良に陥ることもあった。ブース別に机といすがあり先生が定期的に巡回していくという塾に適していること適さない子がはっきりと分かれていた(それは、他の形式の塾に関しても言えること)。勉強が得意でどんどん進んでいく子にとっては合っており、指導者は本当に短時間だけ指導、持ち時間が余ることも(それはそれで素晴らしい)。逆に勉強があまりにも苦手だから「個別指導」に行ったとしても「時間を死守」するタイプの先生にあたると「もっと質問したかったのに・・・・」と消化不良を起こす。でも、それは先生、生徒のどちらが悪いというわけではない。勉強が苦手なのでじっくり・・・という場合は究極は家庭教師がおすすめと言うことになる。「国語はこのまま続けて、3月からは数学は別の塾に行くんです!」と頑張っている生徒を見ると応援すると同時に、「彼(彼女)にとって素晴らしい先生との出会いがありますように!!!」願っている。年度末、年度初めは塾を考える人が多くなる時期。その時に「国語塾」を候補の一つとして入れていただけると幸いである。
2016/03/05 09:06
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
脇に置いておく
人は感情の生き物なので日々、様々なことを考え感じながら生きている。むろん楽しいことや嬉しいことばかりだと最高なのだが、そうではない。悲しみ、怒りなどいろいろな感情が湧き上がってくる。それらがあまりにも大きいと、どう対処していいか分からなくなってしまうのだが・・・・。そんな時にはそれらの感情を「押し殺すのではなく、一旦脇に置くのがコツ。そして十分その感情を客観的に味わって、開放してあげるんだよ」と心理カウンセラーをしている知人から聞いたことがある。とはいえ、単に説明を聞いただけで「はい、そうですね」とはいかないが(苦笑)。どうしても自分との感情の付き合い方が難しくなったら具体的に知人にお世話になるとしよう。さて、答えのない勉強(国語で言うならば文章作成など)は全く同じことが言える。与えられたテーマにそって、細かく計画を立てて書き始めたものの・・・・どうしても進まないということがある。そういう時はいったん、そのテーマを脇に置くのである。そして、冷静に「文章計画」を見直して内容をごっそり変えてみるのだ。最初のテーマを却下しろとは言わないが、取りあえず別の方法を取ってみて再び日をあけて最初のテーマに取り掛かってみる。すると意外と、最初のテーマには無理があったと気づいたり、逆にどんどん筆が進んだりするもの。最初のテーマはボツになることも。それはそれで納得済みのボツなので全く問題なし。こだわることは素晴らしいが、何にこだわるか?(最初のテーマにこだわるか?それとも出来のいい文章を作ることにこだわるか?)が大切。
2016/03/04 11:23
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
具体的
ある実験の動画を見た。その実験内容とは、実験者が被験者に対して次のような指示を出す。「四角形の上に円を描いてください」と。3人の被験者はそれぞれ与えられた紙と鉛筆を使って各々図形を描く。一斉にそれらをオープンにしたところ、一人は四角形と円が離れた状態の図、二人目は二つの図形が接している状態、三人目は二つの図形が重なった図・・・。この実験は何を意味するか?漠然とした指示だと意図が伝わらないということ。例えば「勉強しろ勉強しろ」と親や先生が子供たちにいくら口酸っぱく言ったとしても「何をいつまでに、どのように」を指示しない限り、子供たちにとっては難しい。国語授業では「・具体的な授業・具体的な宿題」を心がけながら毎日のように資料を作ったり授業計画を立てている。時には授業直前に、ふとアイデアが浮かんでギリギリになって資料を準備することも。そうやって心がけていても、うまく伝わらないことがあり反省。とにもかくも周囲にお願い、指示をするときは「具体的に」!さて、仕事では「具体的に・・・」と考えすぎている反動で?!クリエイティブな仕事をしている友人に作品をオーダーするときは「適当に。色はラメ・・・。あとはお任せ」という丸投げでかなり迷惑をかけているが(苦笑)。いやいや、それは相手の感性を信頼しているから。Jさん!いつもありがとう。
2016/03/03 15:40
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
内(だい)
雛祭りが近づくと、あちこちのお店で「明かりをつけましょ~♪ぼんぼりに~♫」というメロディーが流れてくる。良く知られている「うれしいひまなつり」の歌で、2番は「お内裏様とお雛様~♫」と続く。何気にパソコンに「おだいりさま」と入力するときちんと「お内裏様」と変換される。が、意外と自分で書こうとすると書けないのが「内(だい)」。「内」は「だい」という読み方があり、他にも「境内(けいだい)」で使われる。実は○十年前、自身が中学一年生だった時に受けた試験で「神社の境内」の下線部の読み方を書く問題が出てきた。神社だから「けいだい」と読むのだろうと正解を書いたものの(いやいや、内はダイとは読まない!)と勝手に思い込んで「けいない」と書いてしまい×になったことがある。全く同じ問題が、某中学校の期末テストで出てきたのだが・・・教え子たちはほぼ全滅。「境内」=「けいだい」という読み方のみならず「お内裏様」=「おだいり」と読むことを紹介し「内」は「だい」と読むことを彼らにインプット予定。最初から出来る人はいないが、間違いを間違いとして放っておくのではなく、そこから学び2度目は間違えないようにすることが大切。
2016/03/02 08:54
-
Iさん!初コメントありがとうございます!普通に「暗記!」と言われてもなかなか覚えられませんので・・・。明日、こうご期待です?!
2016/3/3 15:31 返信
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
茶わんの中の顔
小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)と言えば怪談話が有名。八雲の名前を知らなくても「耳なし坊一」の話は耳にしたことがある!という人が多いのでは?さて、彼の作品の一つで「茶わんの中の顔」という短編がある。茶わんに自分とは別の人の顔が映るのだが、主人公はそのお茶を飲み込むのである。その夜、茶わんに映った顔本人の幽霊が現われるが、刀で切る。翌日には昨晩、刀で切られたという幽霊の部下(これもやはり幽霊)が現われるが、これも刀で切る・・・という場面で話は終わる。話の続きはおそらく作者(八雲)の中ではあったのだろうが、物語はここで終わっている。正直言って以前は、この中途半端な終わり方?に対してモヤモヤとしていたのだが、最近再び読み返してみると「面白い!」と感じる。なぜならば、以前に書いたように小説の大切な要素は「盛り上がり、裏切り、ドキリ」の「3り」であり、まさにこのすべての「3り」を満たしているからである。究極は最後の終わり方の「裏切り」である。中途半端な?終わり方をすることによって、読者を裏切っているが、そこからどんどん想像が膨らむのである。ここからの続きはそれぞれ皆違うだろうが、このブログを読んで下さっている方はどんな終わり方を想像するか?素晴らしいエンドを思いついたらぜひご一報を。
2016/03/01 14:09
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
長所を生かすには・・・
「素直」であることは長所であり、それはとっても大切なことだと2日前に書いた。ここで気を付けなくてはならないのは「長所」を「長所」として生かすためには「自分軸をもつ」「多角的視点」を持つことだろう。なぜなら「素直」という長所しか持たなかったとすると・・・・周囲の言葉をすべて鵜呑みにしてしまうことにつながりかねない。下手すると、気がついたら「怪しげな壺の購入(苦笑)」「マルチ商法にはまる」「カルトにどっぷりつかる」ということに!ではそうならないためにはどうするか?先にも書いたが「多角的視点」を持つこと。例えば、ニュースを見たり読んだりした時に「本当にそうだろうか?別の見方をすれば○○なのではないか?」と言った具合に常に冷静に判断する術を身につける必要がある。そうすると騙されるなんてことにはならない。自分自身に関していえば、昔から性格が悪い?!おかげで「え?これは言い変えると△△ともいえる。ということは必ずしも良いことばかりではない。」と心の中であらゆることに対して毒づいている。あらゆることを批判しまくるのはこれまた極端で、良くないが、ほどほどのバランスを保ちつつ自分軸、多角的視点を持つことが大切。そのための勉強を国語学習を通してしていると言える。
2016/02/29 12:25
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です