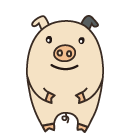小さな国語塾のつぶやき
インフル+エンザ?!
2月末~インフルエンザが猛威をふるっており、この一か月間インフルエンザに罹患して欠席・・・が相次いでいる。「インフルエンザ」の語源は、16世紀のイタリアの占星術師たちが、冬季に流行し春に終息する周期性から流行を星の運行や寒気の影響によるものと考え、「影響」を表すラテン語(influenctiacoeli)にちなんで「influenza」と呼んだことに由来すると言われている。ずーっと昔は、英語では「影響」は「influence」なので、きっと英語の「影響」プラス「enza」という言葉がくっついたに違いないなんて思っていた。というのが、日本には昔から「ベンザブロック」という鼻水や咳などの風邪症状を抑える薬が存在するから。←(エンザが同じだと思っていた)。ちなみに「ベンザブロッック」の語源は「ピリベンザミン」の「ベンザ」+「ブロック」≒「ベンザブロック」らしい。単にピリベンザミンという薬の一部+「抑える」という意味の英語が合わさったのだ。全くお門違いの想像だったが、だからこそ?時々語源を調べてみては、当たっていると嬉しいもの。さて、インフルエンザに罹患した(している)人にとってはこんな暢気なことを言っている場合ではないだろうが、少なくとも国語塾に関しては振替制度を設けているのでどんどん利用してほしい。ちなみに新年度から、中学生クラスが「水曜日 午後7時40分~8時30分」が増えるので振替はもちろんのこと、新規入会も大歓迎。
2016/03/19 18:28
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
高学年の底力
高学年クラスでは、先月に小論文を少し学習し、その際に「長期休みに宿題を出すべきか出さないべきか、理由を付けて述べる」という演習を行ったことはこのブログでも書いたとおり。たまたま4、5日前の新聞で「長期休みの宿題」に対しての様々な読者の意見が掲載されていたのでコピーして紹介。それらを読んで気づいたことや思ったことを述べるという演習を行ったところ、キラリと光る素晴らしい意見が飛び交った。大人の場合だと、つい「新聞に載るぐらいの文章だから完璧・・・?!」という先入観を持ってしまうが、子供たちはというと「この人、意見が飛躍し過ぎててよく分からない。」という鋭い意見も。「具体的にはどんな風に飛躍している?」と突っ込むと「例えば、小学校の生徒会の立候補演説で書記に立候補している人が『僕(私)が書記になったら、明るい学校を作ることを約束します』と言うようなもの。書記の仕事は書くことだから、学校全体をよくすることには直接には結びつかない。だから『書記になって、きれいで分かりやすい字や文を書くことを心がけて明るい学校にするためのお手伝いをします』と言うべきだよ。」という意見。思わず内心で拍手!偏った先入観を持たずに冷静に物事を考えて述べることが出来ることは素晴らしく、成長したなあ~と嬉しかった。この姿勢を保ちつつ次の学年に進んでほしいと期待している。
2016/03/18 14:43
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
枠と粋
昨日は公立入試の合格発表、頑張りが報われて桜が咲いた中学生が多い?と信じているがいかに。さて、まだ3月中旬だが、早いところでは桜が満開になったそうで「へーっ、そうなんだ~」と思いながらネットサーフィンをしていると「これぞ日本の心 枠に楽しむお花見」というタイトルのブログが目に入った。と同時に違和感が!そう、「枠(わく)」ではなく「粋(いき)」が正しいのに・・・・、本文ではきちんと「粋(いき)」と表記されていたがタイトルで間違えるとは残念!この二つの漢字を見ながらふと思ったことが「なんでも枠(決まった型など)は絶対に大切で、それを踏まえたうえでプラスアルファの工夫(漢字で言うならばキヘンの上に点)を加えると粋(風情がある、しゃれた)ものになるということ。芸術作品でも文学においても、お料理でもほんの少しだけ手を加えたり工夫するだけで結果が大きく違ってくることがある。逆にちょっとしたミスですべてが台無しになることも(ブログタイトルがまさにその典型例)。まずは「枠」、そしていずれは「粋」となるように精進。ちなみに「卆」は「卒業」の「卒」の略字である。
2016/03/17 12:37
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
卒
3月と言えば卒業の時期、昨日は十勝管内では卒業式が行われた中学校が多く、小学生に関しては「卒業式でのコメント提出が明日までなんです~」というSOSが相次いだ。さて、卒業とは「業(学び)を終える」という意味なのだが、なぜ「卒」が終えるなのか?「卒」という字を分解してみる。「卒」の上部の「亠」と「从」は、「衣」を表している。「卒」の下部の「十」は、音符の「|」と「ノ」から成り、「しるし」の意味を表している。上部の「衣」と下部の「しるし」を合わせて、「衣服につけたしるし」という指事文字で、人が死んで「衣」の襟(えり)を重ね合わせ、結び留めることを表している文字。そうやって死者の霊が外に出ないようにしている、または悪いものが死体に入り込(こ)まないようにしているという。それが転じて、「おわる」を意味する「卒」という漢字が成り立ったという。また、このしるしのある衣服は、しもべ・兵士にも用いられたので、「しもべ・兵士」の意味も表す。語源を知ると少し怖いような感じがするが、考え見れば「何かが終わるということは、新しい始まり」と言えるわけであって・・・。学業に限らず、何かを卒業して新しくスタートを切るということはどんどんやっていきたいもの。
2016/03/16 10:06
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
使い分け
先日、中学生から「先生、『わかた』って知ってる?」と聞かれた。思わず「ん?若田光一さん?!」生徒「違うよ~~~、ラインでは『わかった』を『わかた』って打つんだよ。他にも・・・・」といくつか教えてくれたのだが、そもそもラインをやっていない自分自身には、そういう言葉を表示させる操作方法はもちろんのこと言葉の意味もチンプンカンプン。「うーん、最近の若い子はまるでバイリンガルだね~~」と感心した。心底「新しい言葉の変化を生み出したり、それらをすぐに習得?するとは特殊能力!」と思ったのだ。念のため生徒には「書き言葉、話し言葉、国語での表記」を使い分けるよう伝えた。大半の生徒はきちんと使い分けを出来ており、時々「え?これって話し言葉なんですか?知らなかった~。じゃあ、書き言葉ではないんですね」という場合もあるが、そういうことを2,3回繰り返せば自然とうまく使い分けが出来るようになり、今更ながら若い子の吸収力に感心している。さて、何が言いたいか?「言葉とは変化する」ものだということを自覚し、それらを使い分けることが大切だということ。時々、「話し言葉」「件名なし」「日本語表記が間違っている」「敬語を使っていない」というメールをもらうことがあり(決して親しいわけではない人から)、その瞬間にズーンとモードが下がる。顔が見えないやり取りこそ、言葉の使い分けをきちんとするべし。※天に誓って書くが、先のようなメールを送ってくる人は国語塾の生徒さんや保護者の方では決してない。
2016/03/15 13:10
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
ペンの色を変える
去年からモノづくりを仕事として起業した友人は、いかにしてお客様に喜んでいただけるかということばかりを優先し、利益度外視で頑張っている。その様子をみた友人の知人が「経営とはなんぞや」から始まり、延々とお説教?をし・・・・友人は話半分で聞いていたそうだ。これを聞いた時に、その時の様子が目に浮かび思わず苦笑い。さて、自分自身も「時には同業者の話を聞くのは勉強!」とばかりに、昨日は講演会に参加。役立つ情報がいくつかあったのだが、そのうちの一つを今日紹介する。国語の記述問題を採点し、直す時は「赤以外」のペンですること。つまり、○×は赤でいいのだが、記述の模範解答は違う色で書くとパッと目に飛び込んできて理解につながる。成程、必死で直したとしても○×の色と同じだと赤だらけになってしまい目立たない。ペンの色を変えるのは面倒?だが、少しの工夫で理解が深まるならばやって損はない。しかも、最近は一本のペンに3色、4色のインクが付属というものが多数あるので、さほどの負担にはならないはず。ぜひトライ!
2016/03/14 16:38
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
自分で自分をだます
先週の中学生クラスで、半分以上の生徒がひっかかってしまった接続語を入れる問を1つ紹介しよう。(本文)「栄養バランスが著しく偏った子が多かったことから、政府はアメリカが提供した脱脂粉乳を学校での昼食時に給食として出した。( )、その後日本の食糧事情が改善され、アメリカの食料提供もなくなったので・・・」※下線部は本文には入っていないが、分かりやすくするためにブログでは入れた。( )には逆説の「しかし」が入るのだが、なぜか皆「すると」を選んでしまった。下線部を見ると分かるように前半は①栄養が偏っている②アメリカが提供後半は①食料事情改善②アメリカの食料提供がなくなったので落ち着いてみると逆の内容だと分かる。皆に上記のように線を引かせてみると皆答えることが出来るのだが・・・・。なぜ「すると」を選んだのかを聞いてみると、ある生徒が「この文の流れだと『すると』しか有り得ません!」とのこと。つまり、今までに読んだことのある文章から、いわゆるフィーリングで選んでしまったようだ。毎回、接続語を入れる問題は前後の主語と述語をチェックするようにと言っているのだが、どうしても長年の経験?からのフィーリングに頼ってしまいがち。ではどうすればいいか?人には「自分で自分をだます仕組み」である「認知バイアス」が備わっていることを理解し、自覚することと少しは役立つのではないだろうか?「認知バイアス」については詳細は割愛するので、各自で調べてみてほしい。
2016/03/13 12:19
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
大きな力
昨日、生徒にいきなり「先生は神や幽霊って信じますか?」との質問。「うーん、神や幽霊うんぬんというよりも宇宙、自然、大地、人の想い、といった目に見えない何か大きな力(ちなみに中学2年生の教科書「走れメロス」にも出てくる、大きな力)は信じているよ。それを人によっては「神」と呼ぶ人もいるだろうし「幽霊」という人もいると思う。ただ、自分はその大きな力を「神」だの「幽霊」だのとは限定しない。あえて言うならばサムシンググレートと呼ぶかな。サムシンググレート(筑波大学名誉教授 村上和雄氏が提唱している言葉)は感じているし信じているよ。」と返答。すると「さすが、国語の先生!僕と一緒の考えだね!!!」ととっても褒めてくれた。いつも褒めてくれる彼に対して感謝するとともに、彼の考えの素晴らしさには思わず感服。なぜこういうことを質問したのかと聞くと、先日、街で宗教家に「神を信じますか?」と聞かれたとのこと。その時に「僕は自分の内側に神があると信じてます」と答えたらとってもとっても感心されたとのこと。そりゃあそうでしょう~!将来は教祖様としてスカウトされるかも?!(笑)さて、サムシンググレートの存在を裏付けるような出来事が。次の授業終了後、恒例のくじ引きでは3人中1人がなんとなんと5回連続で「あたり」を出した。同じ条件にも関わらず他の2人は何度引いても「はずれ」・・・(他の二人に同情し、3回まで引いていいことにした)。今日も楽しく不思議な授業風景だった。ちょっと?かなり?風変りの国語塾、興味がある方はぜひ体験を。
2016/03/12 00:29
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
人から習う
昨日、プリント演習をしていた中学生から「先生、謙虚ってどういう意味ですか?」と聞かれた。とっさに「①へりくだること②素直に相手の意見を受け入れること」と、いわゆる辞書の内容そのものを答えそうになったがグッと飲み込んだ。「謙虚」=「へりくだる」と言われたところで、次は「じゃあ、へりくだるってどういうこと?」となるのが目に浮かんだから。結局、「例えば、何か美味しいものを沢山作った時に、美味しいから人様に差し上げようという気持ちが起ったとしても昔の日本人は特に『つまらないものですが、どうぞ召し上がって下さい』みたいに表現するときがある。直接『美味しいから』とは言わずに自分の行動を少し下げて表現したりする、それが謙虚ということ。他には・・・・」と必死で具体例を考えて説明したところ、「成程!」と納得してくれた。ふーっ。その時に「何かを知ったり習ったりするときには、自力で頑張る時にはとにかく詳しい解説書や参考書を選ぶこと。ただし、詳しくて分厚い?解説書や参考書を読む自信がないという場合は人に教えてもらうのが一番だ」と強く感じた。むろん自力で努力することは大切で、人任せだけだと力がつかないのは事実。自力で努力することと人から学ぶことのバランスをうまく取ることが何事においても大切。
2016/03/11 13:00
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
サナギ
昨日からプッシュが増えており、しかも何日分もまとめて読んで、プッシュをした下さった方が何人かいらっしゃり・・・・本当の本当に嬉しく、「有難うございます!」以外の言葉が見つからない。ラジオ中継のおかげだと、担当者のMさんにも改めて感謝!Mさんの進行がお上手で、生徒さんはもちろんお迎えのために来てくれた弟君も飛び入り参加での和気あいあいとした中継。本当に皆様にはこの場を借りて改めてお礼を申し上げたい。さて、昨日保護者の方からチラリと「最近、子供がなかなか文章が進まなくて・・・」というお悩みが。表現をすることが大好きなタイプなのに、なぜ?と考えて込んでしまっているご様子。結論を言うと、全く心配なく、「筆が止まってしまう」という時期はよくあること。何週間、あるいは何か月?かすると、そのスランプを脱して大きく成長しているはず。例えば、美しい「蝶」は幼虫から蝶になる前にサナギになって何日もじっと動かずに過ごす。それは美しい蝶になる前の準備として不可欠な時期。文章においても同じで、今までは自由に表現していたのが、さらにステップアップのための用法を学んだり、今までに取り組んだことのない「お題」を出されて必死で変わろうと努力している状態だと言える。指示を無視して今まで通り・・・だと一見「おおっ、さすが書くことが得意なんだ~」となるが、長い目で見ると成長はしづらい。そう言う意味では素直に頑張る生徒さん(保護者の方からすると我が子)を信じて見守る頃が今、出来ることの最善か。
2016/03/10 12:50
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です