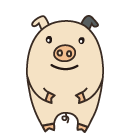小さな国語塾のつぶやき
詩の主題
いつも書いてることだが「詩」は難しいと思う。なぜなら「詩」とは自然の美しさや人生の喜びや悲しみなどの気持ちを、短い文章や比ゆを使って表現しているから。「詩」の問で必ずと言っていいほど聞かれるのが「主題」。題名、くり返されていることば、印象的なことばをヒントに・・・ということは一般的に良く言われている。今回は特に「題名」に着目。例えば、世の中には数多くの「英語塾」が存在する。一言で「英語塾」と言っても何を中心に学ぶのかは分からない。「英会話」「文法中心」「ゲームなど中心」「机といすを使って勉強する」「少人数」「大人数」「大人向け」「子供向け」「学校の勉強中心」など直接教室に問い合わせてみないことには分からない。とまあ、「英語塾」だけでは詳しくは分からないが、それでも少なくとも「国語」をイメージする人は皆無。つまり題名を見るだけで大まかな主題が分かるということ。中学3年生の教科書の始めに、谷川俊太郎の「春に」が掲載されている。主題を選ばせる四択の問題がワーク類には必ずのっており、選択肢を読めばどれも正解に思えてくる(←そのように意図して作成している)。ここでヒントとなるのが「題名」の持つイメージ。「春」と聞くと一般的には「新しい生命」「始まり」「それにともなう様々な想い」・・・・というイメージが湧くだろう。逆に「冬」というと「こもる」「寒い」「さみしい」・・・といった感じか。ただし、これも以前に書いたが「山」「扉」という題名は要注意!山登りに対するノウハウ、気持ち・・・というよりも「山、扉」=「困難」を表していることが多い。いやはや、国語(特に詩)はやはり難しい。
2016/06/02 14:22
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
ニックネーム2
昨日は人様に関するニックネームを書いたが、今日は紹介を兼ねて自分のニックネームを紹介する。若い頃から個性的だったため、様々なニックネームを付けていただいた。代表的なものとしては「仏」「怪物(←類まれな体力を保持しているため)」「鬼」「天使」「モンゴル人」「宇宙○○」・・・・。他にも沢山あるのだが、一番お気に入りは「宇宙○○」。○○に関しては想像にお任せする(素晴らしすぎるため、畏れ多くてここでは書けない。名付け親のJさん!ありがとう!)それにしても自分で書いてみて気付いたのだが、あまりにも異形の物と言ったニックネームが多いような。ウーン、喜ぶべきか悲しむべきか?いやどう考えても喜ぶべきことだろう。生徒たちが陰でどんなニックネームをつけようが、全く気にならないが、もしも素敵なニックネームを考えてくれた場合はいつでもお知らせ願いたい。その場合は豪華賞品あり?!そして、このブログを読んで「え?一体どんな人が国語教室を主宰してるの?」と気になった方はぜひぜひ体験、見学受付中。今日は国語ネタとは全く関係ないことを書いてしまったが、明日からは心を入れ替えて真面目な話題に戻る予定。こうご期待?!
2016/05/31 21:01
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
ニックネーム
先日、保護者の方からのメールで「丸焦げチョコポッキーみたい・・・」という表現が。この「丸焦げチョコポッキー」というのは実息子に対しての愛のこもった?!ニックネーム。この生徒は長身、スリム、色白という風貌だが、最近は外での活動が多くなってるため日焼けしている。それを先のように表現しており、思わず大笑い!チョコポッキーとは、ご周知のとおりグリコの超ロングセラーで皆から愛されるお菓子の名前。彼の見た目のみならず、内面も表しており(皆から好かれて可愛がられるタイプ)うまい表現だなあと感心した。そう言えば、夏目漱石の「坊ちゃん」の登場人物は「赤シャツ」「野だいこ」「マドンナ」「山嵐」「うらなり」・・・とニックネームが使用されており、ニックネームを聞いたり見たりする側としては想像力がかきたてられていいかも?と妙に納得。かくいう自分自身も実は生徒のことをイメージする時にはニックネームが浮かんでくる。※このニックネームはあくまで自分自身の中で勝手に付けた名称。例えば「今日は、○曜日だから・・・・あ、イケメン君の日だ」とか「おおおっ、癒し系の日」「ナイスガイ達」「可愛い子ちゃん達」「メガネが良く似合う○○」「好感度No1」等々。これを読んで頂くと分かるように95パーセント以上、良いニックネームだけを付けているのでご安心を?!(なぜ100パーセントにしないか?基本的に世の中で100パーセントは有り得ないと考えているから)。生徒諸君、自分のニックネームを知りたい時はこっそりとご一報を(笑)。ちなみに冗談の通じる生徒一人には本人のニックネームを伝えている。とっても喜んでくれたのでホッ。
2016/05/30 03:48
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
一番身になったのは・・・
先週の中学生クラスでは主題が最初から与えられている文章を準備。その主題文が具体的にどこに書いてあるかを探すという今までとは逆バージョンをやってみた。この時に使った資料が「脳はなにげに不公平」(池谷裕二著 2016.3.30一刷)という新刊本のP212。主題(タイトル)は「感情は表情よりも身体に表れる」。先日もこのブログで少し紹介したが、2012年度から採用された中学1年生の国語の教科書に「笑顔の魔法」という文章があり、それを執筆したのが池谷氏で、今回の「感情は・・・」は「笑顔の魔法」の続編にあたる。実は今回の授業企画の中で、一番勉強になったのは生徒ではなく自分自身だったような気がする(苦笑)。たまたま手に取った新刊本に国語教科書に掲載されている文章の続きがあったので授業で使ったわけだが、もしも国語教科書に「笑顔の魔法」がなければおそらく「感情は・・・」の内容はスルーしていただろう。①単なる文章としてしか認識しないであろう内容をしっかりと頭に入れることが出来た。②かれこれ10年近く前に某カウンセラーの方が(著書複数あり、TV出演するなどかなり活躍されている方)「内面(心理的)なことを解決するには、まずは外部(身体)からアプローチした方が有効」とおっしゃってたことが、ようやく今になってはっきりと納得が出来た。生徒はにとってはおそらく「へーっ、教科書の続編か~」「成程、主題を探すには接続語のみならずキーワードが大切なんだ~」ぐらいしか残ってないだろうが、年齢を重ねている自分には先に述べた2点を実感でき、生徒や授業のため・・・とやっていることを実は自分が一番身につけている?!と嬉しい気持ちになった。
2016/05/29 15:29
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
古典は役立たない?!
百人一首を50枚以上覚えているという強者T君。おそらく古文はバッチリ?と期待しながら古文を一題解かせてみた(本年度から入塾のため、どのぐらいの力量かを知るため)。とてもやる気があり、頭脳明晰のT君なのだが思わず「これは解けてほしかった!」とつぶやいてしまう場面が・・・。とはいえ、解けなかったのはT君の責任ではなく、考えてみると古文(古典)は中学校の授業ではあまり詳しくは学ばないけれど、試験にはそれなりのレベルの物が出題されるという厄介な分野。生徒によっては「古文(古典)なんて勉強しても仕方がない!自分は将来文部科学省の役人になて古文廃止を訴えます!」とものすごい剣幕で演説することも。では、本当に古文(古典)は役立たないのか?一般論としては「古人の生き方を学ぶことが出来る」となるが・・・。とはいえ、それは説得力がない。「生き方」を学ぶならば身近で尊敬できる人間で十分、敢えて古典から学ぶ必要はない。ではなぜ古文(古典)を学ぶ必要があるか?正直言って答えは出ないが、一つだけ言えるのは「大手企業の経営者たちは大抵『古文』『古典』を愛読している」ということ。メインは中国の孫子の「兵法」孔子の「論語」。日本の古典では「平家物語」、「徒然草」、「方丈記」など。「将来は○○(誰もが知っている有名企業)に就職したい」と目を輝かせながら語ってくれたT君。直接自分自身の「生き方」等に影響を及ぼさなくても、大手企業に就職を考えているならば「古文」「古典」について知っておいて損はない。つまらない?古文を勉強すると必ず役立つ日が来ると信じて皆ファイト。
2016/05/28 02:20
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
プロはだし
「プロはだし」という言葉がある。「プロも裸足で逃げる」の略で、意味は【本職(プロ)の人よりすごい腕前ということ。「裸足で逃げる」・・・、その道の専門家でさえ、とてもかなわないと見て慌てて靴をはくことも忘れて逃げ出すさま。非常にすぐれていることのたとえ。】お恥ずかしいながら、初めて「プロはだし」を見た時に「プロは出汁」つまり「(料理の)プロは化学調味料ではなく、きちんと出汁をとる」だと思い込んだのだが、さすがにそれでは意味が通じない。おかしいと思って調べた次第。本来の意味を知った時に感じたことが、裸足で逃げた人は謙虚な姿勢があるなあということ。世の中には大した実力がなくても、免許、資格を持っていることに胡坐をかいている人がごまんといるが、自分以外の人の仕事を見て「かなわない」と感じて逃げるとは今後の成長が期待できる。かくいう自分自身も裸足で逃げなくて済むよう、どうやって授業構成するか?どんな資料を作るか?何がベストかと常に思案中☜周囲から見るとただ単にボケーッとしてるとしか映らないだろうが(苦笑・・・いや実際にボケーッとしている時間の方が長い?!)。自分のことは棚に上げて、何を作っても(手工芸)まさに「プロはだし」の友人を「プロデビューしよう~~~~」と焚き付けたことも。人のことより、自分の成長に集中しようっと。
2016/05/27 12:50
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
怖いもの見たさ
有名な日本昔話に「ツルの恩返し」がある。「絶対にのぞいてはいけない」と言われてるにもかかわらず、おじいさん(地域や話によっては若者)は覗いてしまう・・・。「のぞくな」と言われるとなおさらのぞきたくなってしまう、いわゆる「怖いもの見たさ」を本能的に人間は持っている。さて、昨日の中学生クラスでは前半10分間は配布した資料に集中させるため「私語厳禁」とし、質問以外の私語をした場合はペナルティーという条件で授業開始。おかげで、皆スムーズに課題に取り組めたのだが・・・。10分を過ぎてから、なぜか突然にS君が「ゴキブリ」について質問してきた。それからというものなぜか「ゴキブリ」談議に花が咲き・・・。生徒たちは皆北海道出身のため本物を見たことがなく、話で聞いた、ユーチューブで見ただけなのでいわゆる「怖いものみたさ」の心理だったようだ。さらには発展して、指導者に対して「過去の成績」はいかなるものだったか?などなどエスカレート。取りあえず返答は保留しているが、来週になってもまだ引きずる?!ならば「なぜ、指導者の昔の成績を知りたいのか?相手を納得させるような理由を原稿用紙1枚(400字)以内でまとめること」という課題を出そうと企んでいる。知らなかったことを知りたいという気持ちをダイレクトに国語の内容に向けるのは大変だが、「知りたい」という好奇心を尊重しつつ、なおかつ国語力を付ける方向に持って行こうと日々奮闘中。
2016/05/26 12:33
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
何これ?
「何これ?面白そう」という好奇心が脳の性能を高めるということが最近科学的に実証されている。実は子供や若い人たちが、何でも覚えることが出来る・・・というのは好奇心の有無が大きく関係しているらしいというのだ。確かに、大人、さらには老齢になっていくにつれて無意識のうちに「ああ、それ知ってるよ」「つまんない」と感じてしまい、本来ならば既に知っていることよりももっと深い有益な情報があるかもしれないものを見過ごしてしまう、覚えられないという結果になる。「素直」なタイプこそ伸びる所以の一つが好奇心の有無とも言える。また、自力で勉強していると長々と書いてある解説を読んでも、なかなかワクワク感が湧いてこず頭に入ってこない。視覚のみならず聴覚などをフル活用できるような対面授業、衛星授業が有益だと言える。さて、国語の授業ではいかにして生徒達に「何これ?面白そう」と思ってもらえるか?と毎回工夫を凝らしているつもりだが・・・意外な反応が返ってくることがあり、それはそれで面白い。例えば先日の中学生対象の授業では、前もってテーマやポイントを板書していたところ、それを見た生徒が「ヤッター!!!『古』という字が見当たらない。ということは今日は古文はしないんですね!え?何なに?今日のテーマは「○○」ですね・・・」と反応。これから学ぶことに興味を持ってくれたことは嬉しいが、複雑な気分であった(苦笑)。
2016/05/25 11:42
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
言葉を分解
漢字や言葉を分解すると面白い!例えば、先日知った言葉としては「休む」。「『やすむ(休む)』というやまとことばは、分解すると『や(屋)+すむ(住む)』だとされています。『家のなかにいること』という意味です。【やまとことば50音辞典 高村史司著】」という文章を読んで成程~~~と妙に感心した。最近とにかく家の中にずーっとこもっており極力外出しないようにと行動している自分は「引きこもり一歩手前?」と少々ネガティブな気分になっていたが、「そっか~、自分は休んでいるんだ!仕事、休憩共に家の中でしているだけなんだ」と前向き解釈。相変わらず今日も家で「休み」ながら…他の言葉を分解して遊んでいる。家に関する言葉と言えば「居候(いそうろう)【他人の家に世話になりながら食べさせてもらうこと】」。これも「居」プラス「候(そうろう)」☞「候」は「ございます」の謙譲語なので「居させてもらってます」という謙虚な表現だと気づいた。いつから「厄介者」という意味になったのかを調べてみたところ明治時代以降という。言葉は変化するので現在の意味からは若干かけ離れてしまうが、漢語を分解して原語をたどるとなかなか興味深い。しばらく「家住む」が続きそうな予感(苦笑)。
2016/05/24 15:05
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
「言挙げ」
「言挙げ(ことあげ)」思想を皆は知っているだろうか?「言霊(ことだま)」と並んで、古代の日本人が言葉の力を恐れ敬った証拠、考え方が「言挙げ」思想。「言霊」は「私たちが口にした言葉には魂が宿っており、口にした通りのことを実現する力を持っている」という考え方。それゆえに、平安時代ではむやみに人の名前を口に出したり書いたりしてはならないという風潮があった☞古典では主語が省略される…ということは以前にブログで紹介した通り。さて、「言挙げ」は「言霊」ほどには知られていない考え方で「自分の意思をはっきりと声に出して示すこと。ところが、その言葉に誤りやおごりがある時は、悪い結果がもたらされる」意味のため、使うことをためらい、あまり浸透していない。古代の日本人は、個人が「ことあげ」をすることは神の意思を超えることであり、それは許されないと感じていたようだ。世界各国の人から「日本人は自分の考えをはっきりと言わない」と批判されるが、それは決して消極的な態度の表れではなく、言葉を大切にしている日本人独特の「謙虚さ」だと思う。とはいえ「言挙げ」を気にするあまり言いたいことを口にしないというのはもったいないこと。何事も言ってみないと伝わらない、例えば高級レストランに行ってオーダーしたいお料理をじっと念じたところでお皿が出てくるわけではない。きちんと口に出さないことには好きなものを食べることが出来ない、店員さんから「え?この人がこんな高いワインを?」と思われることなんて気にしてはいけない、今はふさわしくなくてもいずれ高級食材に見合うように成長すれば「言挙げ」ではなく「言霊」になるのだから。
2016/05/23 13:28
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です