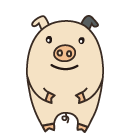小さな国語塾のつぶやき
解き直し
どの科目も「反復」「解き直し(間違ったところのみならずもう一度すべての問題を解くこと)」が大切だと言われているし、実際その通り。ただし、国語に関しては解き直しをする際に本文の内容は既に頭に入っている、問についても場合によっては答えを暗記してしまっていることもあり、果たして「解き直し」は有効か?結論を言うとやり方を間違えなければ「解き直し」をすることはかなりの国語力アップにつながる。ただ単に暗記力を試すような「解き直し」では全く意味はない。正しい方法というのは「なぜ、この答えになるか?」を意識し、一回目では間違えてしまった問題に関しては「どんなふうに解説に書いてあったか」「どんなふうに直接指導を受けたか?」を頭の中で再現しながら、「~~という理由でこの部分と別の部分を組み合わせて、記述する」「…の部分が間違っている(本文に書かれていない)から×」と言った具合にすることが大切。「なぜその答えになるか」というプロセスをしっかりと意識しながら2度目、3度目をやってみるとかなりの力がつく。ヤマ勘で正解…ということも時にはあるだろうし、それはそれでラッキーだが、そう言った問題に関しても2回目、3回目ではきちんと論理的に答えを導き出せるように何度も挑戦してみよう!
2016/06/11 02:11
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
グレる
「貝合わせ」という遊びがある。それは、平安時代から「物合わせ」(似たものを合わせて遊ぶ)として、貝の中に文字や絵を描いて遊ぶ風習をいい、男と女の上の句、下の句のやりとりの道具として盛んに用いたという。古典絵巻や古典漫画には「貝合わせ」の様子が描かれていることが多い。その後、蛤(はまぐり)が必ず一対であることから貴族や武士の間で現在のトランプゲームの「神経衰弱」に似た、出し貝と地貝を合わせるゲームが行われるようになった。さて、今はほとんど死語になってるが「グレる(反社会的な行動をとる、不良になる、素行が悪い)」という言葉が昔あった。実はこれは、「蛤(はまぐり)」をひっくり返して成った語「ぐりはま」の転である。 「ぐりはま」の「ぐり」が変化し「ぐれ」、「ぐれ」に活用語尾「る」を付け、動詞化したものである。これらの語は、ハマグリの貝殻をひっくり返すと合わなくなることから、物事が食い違う⇒反社会的、不良、素行が悪いという意味になったという。自身は「グレ」たことはないと自覚しているが、職業柄?!「先生、見た目がワル!」「もしかしてどSですか?」などと褒められると思わず「グレる」という言葉を思い出した次第。それにしても、この言葉を使うとなると・・・世代がバレそうだが、生徒には「平成生まれ!」ということにしている。
2016/06/10 02:51
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
「ヤバい」と「まずい」
「ヤバい」という言葉は昔は「良くない、都合が悪い」という意味のみで使われていたが、最近は強い肯定のでも使われる。例えば美味しい料理を食べた時に「何これ?ヤバくない~?」と言うと最近では「とても美味しい」という場合でも使われる。言葉だけを聞けば「え?美味しくないの」それとも「美味しいの?」どっち?となるが、その場の雰囲気や表情から判断することになる。さて、美味しくないことをダイレクトに表現する言葉としては「不味い(まずい)」がある。こちらも「美味しくない」以外にも「都合が悪い」という意味がある。つまり「ヤバい」と「まずい」は否定の意味を持つという点では同じだが、「まずい」は肯定の意味と持たない。自分自身は古い人間なので、正直言って「ヤバい」を使いこなすことは苦手で、昨日はとっさに「まずい」という言葉が頭に浮かんできた。最近、ブログを読んでくれている方々が固定されつつあるし、基本的には大人の人が大半…と思い込み、かなりの内輪ネタだったり、結構辛辣なことも書いているのだが・・・。超ナイスガイのT君が「僕、先生のブログ読んだことあります。生徒のことは名前を伏せて結構書いてますよね。」というコメント。思わず内心「ま、まずい。え?なんで?だってTはパソコンもスマホも自分専用は持ってないはずでは?」とかなりの焦りが。親に時々見せてもらうことがあるとか。T君の前では「優しい先生」?的な仮面をかぶっているはずが・・・少々仮面がはがれつつある?!と思ったが時すでに遅し。いえいえ、T君は最高にいい子なので今後も優しく接する予定?!!
2016/06/09 12:35
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
ペースメーカー
昨日は、中学年と高学年(国語塾に通塾中)の二人の子育てを頑張っている保護者から嬉しいメール。二人とも、学校で「運動会」の作文を書いたところ、早く書くことが出来たり、内容が分かりやすいと先生から褒められたとか。特に中学年のお子さんに関しては、書き出しなどを保護者が確認したところ、明らかに以前よりも成長ぶりが見られたとのことで文章を一部転送して下さった。具体的で分かりやすく理由も書かれており成長ぶりが著しいと感じた(その子を読書感想文講座で担当させてもらったことがある)。国語塾のおかげです・・・とおっしゃってくれるのだが、ひとえに本人たちの努力の賜物。お教室の指導者というのはマラソンで言うならば「ペースメーカー(一定のペースで走ってマラソン選手を引っ張る人)」といった役割、補助的な存在にしかすぎない。マラソン選手にとって、ペースメーカーが存在することによって無理なスピードでスタートして後でバテるということがなくなり、無理なく完走しやすくなるが、それでも結局大会当日までに必死でトレーニング(努力)して本番に挑み完走するのは本人に他ならない。作文、その他の勉強もしかりで・・・いくら周りが働きかけ、仮に超一流と呼ばれる指導者に指導してもらったとしても本人がその気にならないと何も残らない。もしも一流の指導者のおかげで誰でも伸びるならば一流講師の授業を衛星放送で受けた生徒たちは全員成績がアップするはず(でも実際はそうではない)。ペースメーカーとして少しだけ生徒たちのお手伝い、それによって本人たちが頑張り、結果を出せるということは何にも代えがたい喜びである。
2016/06/08 11:50
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
妄想力炸裂
「更級日記」が面白い!これは平安時代の女性、菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)が書いた日記なのだが、とにかく妄想力炸裂!笑えて、共感できるのだ。ああ、今も昔も皆同じだなあと。一部を紹介する「かろうじて思ひよることは、いみじくやむごとなく、かたち有様、物語にある光源氏などのやうにおはせむ人を年に一たびにても通はしたてまつりて」(現代風に訳すと:セレブでイケメンの光源氏みたいな彼氏が欲しいわ~そんな人なら一年に一回のデートでもいい・・・・)。ただし、現実は親たちが決めた6歳年上の普通の男性と結婚することに。この辺りはというと現代とは若干事情が異なる。現代は夢を見ながら独身で過ごすことOK、また自分で結婚相手を決めることも出来る。実際に友人(女性)がまさに妄想力炸裂で「いつか白馬の王子様が迎えに来てくれる・・・」と常に夢を見ていた(現在彼女は独身)、別の友人(男性)は「絶世の美女と結婚する」と妄想し、実際に美人と結婚した(奥様を見たことはないが、地域の美人コンテストで入賞するぐらいの美貌だとか)。つまり、妄想力炸裂タイプが世の中に存在することは今も昔も変わらないが、今は妄想を妄想で終わらせることなく実現できる可能性があるという点が素晴らしい!!で、自分自身はというと・・・・池田隼人の「所得倍増計画」をもじって「国語塾生徒倍増計画」(ただし、イケメン、ナイスガイ、可愛い子ちゃん限定?!)という妄想力炸裂中。
2016/06/07 12:18
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
処世術
平安時代を代表する女流作家、紫式部(「源氏物語」の作者)は中宮彰子様にお仕えしていた。有る時、紫式部は同僚に「日本紀の御局(にほんぎのみつぼね)」というあだ名を付けられてしまった(ニックネームとあだ名は同義語だが、ニュアンス的にあだ名の方がマイナスイメージとして使われているので、今回は「あだ名」を使用)。「『日本書紀』を講演する大先生」といういう意味で「なによ、自分の知識をひけらかして、頭に来るわ」といったいじわるな意味が込められている。そこで、紫式部は「漢字なんて「一」も書けないわ~」というトロいキャラを演じることによってうまく乗り切ったという。まさに「能ある鷹は爪隠す」を実行している。では、どんな場合でも謙遜した方がいいのか?と言えばそうとも限らない。「爪」を隠し過ぎるとチャンスを逃してしまうこともあるだろう。例えば、紫式部と並び称される(よく比較される)清少納言(「枕草子」の作者)は逆に漢文の知識を上手にひけらかす?ことによって、教養豊かな中宮定子様から信頼されて可愛がられている。結局は、バカになった方がいい時にバカになれるかどうか?がその人の「能力」「人間性」の高さを表してると感じる。自戒を込めて。※本来6月1日付のブログだが、誤字を訂正したため日付けが更新されている。
2016/06/07 00:06
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
自分にあだ名
ニックネーム、あだ名は「対象を別の言葉で言い変えたもの」つまりは「比喩表現」!国語力をアップさせる方法の一つとして、あだ名を考えるというのは有効か。とはいえニックネームやあだ名は基本的に他人に対しての呼び名で、場合によっては人を傷つけることもあるのでその辺りのバランスはほどほどに。さて、自分自身へあだ名やニックネームをつけると意外と思わぬ副産物が。どういうことか?結論を言うと自分自身を客観視することが出来、しかも目の前に立ちはだかる事象に対して冷静に対応できるようになるということ。どんな人間でも生きているといろんなことがあり、時には泣き言を言いたくなることもある。そんな時、自分自身は関東在住の年上の友人に淡々と現状をメールして聞いてもらう。友人の素晴らしいところは決して特定の人や物を批判するのではなく、ただ事実を受け止めてくれてさらには時々ドンピシャのニックネーム、あだ名を付けてくれること。最近では「苦行僧の修行」というコメント。思わず、それを読んだ時に成程~~「自分は苦行僧なんだ!じゃあ、さしずめ今は千日行中?あと何百日?!」と半ばふざけ乍ら自分を客観視、さらには冷静になると打開策の一つが見つかった!例えば、自動車事故において正面衝突するとダメージが大きく、場合によっては命を失うが、それ以外だと車は大破しても自分は無傷ということがある(経験者は語る)。つまり、自分自身にあだ名をつけて客観視(正面からではなく別角度から見る)ことは意外と有効で大切なことだと感じる今日この頃。色んな場面で国語力を付ける訓練は出来るもので、しかも生活に役立つこと間違いなし!
2016/06/06 23:23
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
好きこそ・・・
ブログを書き続けて3年あまり・・・数にすると838件、一年間のうち3,4日留守にする間だけお休みし、それ以外は毎日更新。つまり365日のうち360日は書き続けている。その様子をみて最近、保護者や昔(なんと20年以上前)の教え子ちゃんなどがねぎらいのメールを送ってくれて本当の本当にありがたい。義務で続けているわけではなく単に好きだから続けてこられただけなのだが、それを毎日懲りずに?読んでくれ、しかもねぎらいの言葉をいただけるとは本当にありがたいの極致である。「好(す)きこそ物の上手(じょうず)なれ(好きな事にはおのずと熱中できるから、上達が早いものだ。)」という諺があるが正直言って上達しているかどうかは別として、好きだから続けられるというのは間違いない。とはいえ、実は・・・「書く」ことはずっと苦手で中学、高校時代の夏休みは「読書感想文」が最大の悩みの種。高校2年時に「小論文講座」を受けるかどうかを先生に相談したところ「文章を書くには才能が必要」という冷静な言葉を頂戴し、ガクーンと落ち込んだことも。でも、受験で必要なのでやむなく?「小論文講座」を受け、「型」を学び、簡単な要約の練習に始まり、努力していくうちにいつの間にか好きになっていた。何が言いたいか?小中学校時代に文章を書くのが苦手だからと言って「才能がない」「キライ」かどうかは分からない!☜経験者は語る。好きこそ…の前にまずは「好き」になるかもしれないチャンス、きっかけが見つかるよう応援させていただこうと張り切っている。
2016/06/05 00:45
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
善
「善」という漢字は中学2年生で習う漢字だが、最初から正しく書ける中学生は意外と少ない。なぜか?「美」と同様に「ソ+王」を先に書いてから下を書くと勘違いしてしまうから。採点側は縦線がずれているかどうかを必ずチェックするので書き順が合ってるかどうかがすぐに分かる。正しくは「羊+ソ+一+口」。どうしても自分一人で勉強していると気づかないことがあるので、チェックは第三者にしてもらうのがベストだろう(学校の先生、塾の先生、親など)。さて、「善」といえば・・・人は生まれながらにして善なのか悪なのかは昔から(特に中国)では対比されている。最近は科学的に考察されており、面白い結果が。「直感」と「反射」、どちらも早い判断だが、わずかに直感の方が反応が速いことが知られている。つまり「直感」はより生命の本質に根差した瞬時的判断だと言え、直感的に決定すると、自分中心的な行動よりも他人を利する行動が増えるという。この結果からだと、人は生まれながらにして「善」だとなる。孟子(中国の思想家)は「人間の道徳的本性は善であり、これが隠されて悪が生まれる」と説いている。幸い、通塾してくれている生徒の大半はまだまだ「善」が隠されていないようで毎日癒されている。それが証拠に、間違いやすい四択のパターンを中学生のS君に説明していた時に「え?」と思わせるような優しい発言。すかさず「そんな風に考えることが出来るって素晴らしいね」と伝えたところ本人はキョトン。「僕…さっきのセリフは無意識に言ったのでよく覚えてません」とのこと。無意識、そう直感での発言は「善」そのものであった。☜抽象的過ぎて理解に苦しむかもしれないが、そこはご想像を。
2016/06/04 14:38
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です
ひらがな表記
小説や詩では、敢えて「ひらがな表記」にこだわっている作品がある。あるいは漢字表記とひらがな表記という二種類に分けている場合も。なぜか?①詩や作品全体にやわらかさを出すため②子供らしさをだすため、といったこの二点が基本になる、つまりこの二点は公式として丸暗記。え?丸暗記と思われるかもしれないが、国語だから適当に解ける・・・わけではなく、答えとして求められていることが決まってるので覚えてしまった方が良い。例えば、数学だと公式を自分なりに導くことが出来たとしても、毎回毎回ウーンと考えながら沢山式を書いて導き出すというわけではなく「公式」を覚えるだろう。それと同じで、「国語=日本人だから適当?にやれば解ける」のではなく「公式」として覚えることも時には大切。小六の生徒にひらがな表記が多い「詩」のプリントを出してみたところ、見た瞬間に「え?何これ~?ひらがなばっかり~~~」といきなりの鋭いコメント。問に「なぜひらがな表記が多いか?」というものがあり、むろん見た瞬間に正解をした。さすが(拍手)!ちなみに中3の教科書の「立ってくる春」では「立春」「りっしゅん」と二種類表記がある。これは「まだ小学生の『私』には、祖母の言う『りっしゅん』の意味が分からないことを読者に示したいからである。」当然、学校の授業でも強調されているだろうし、ワーク内にも出題されている。公式②が基準となっていることを理解し、丸暗記!
2016/06/03 12:26
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です