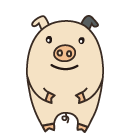小さな国語塾のつぶやき
俳諧と俳句
「柿くへば 鐘が鳴るなり 法隆寺」は正岡子規の俳句で、松尾芭蕉の「古池や 蛙飛び込む 水の音」と並んで俳句の代名詞として知られている。が、厳密にいうと松尾芭蕉が生きた江戸時代には「俳句」というものは存在しなかった。俳諧というのは連句形式【和歌の上の句(五七五)と下の句(七七)をそれぞれ別人が詠むという遊戯的な試み】が主流であった。発句(最初の五七五)のみを独立して鑑賞するようになり、低俗なレベルから文学的レベルに引き上げたのが松尾芭蕉だと言われている。つまり、芭蕉の時代にはまだ「俳句」として独立した文学や言葉がなかった。しかし明治時代になると、正岡子規によって、従来の座の文芸たる俳諧連歌から発句を完全に独立させた個人の文芸として、近代の俳句が確立された。そんな功績もあり、松尾芭蕉と正岡子規という名前とその作品は誰もが知ることになった。
2014/11/24 11:04
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です