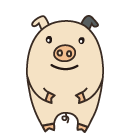小さな国語塾のつぶやき
古文の「の」
古文とは日本語ではなく外国語だととらえるほうがよいと常々思う。以前にブログ書いたが(4月22日)、古語と現代語では同じ表記でも意味が全く違う、下手すると逆になることがあるので、この際「古文は外国語」と割り切って重要な言い回し、単語を覚えたほうがいいと感じる。単語に限らず格助詞もしかりで、現代語の「の」は「~のもの」という所有の意味で使われることが多いが、古文では「の」は主語をあらわす「が」と訳すとうまくいく。たとえば「雪の降りたる・・・」「は「雪が降っている」「雲のたなびきたる・・・」は「雲がたなびいている」と訳になるのである。古文の「の」が100パーセント主語をあらわすかというとそうでもないのだが、とにもかくも現代語とは分けて考えるということを意識すると意味をとらえやすい。ぜひお試しを。
2014/06/30 13:10
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です