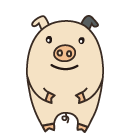小さな国語塾のつぶやき
虫
3月上旬の頃を「啓蟄」といって、冬ごもりしていた虫たちが穴からはい出てくることを言うが、北海道はまだ雪が積もっている頃。だが、3月下旬ともなると本州に遅ればせながらも雪がとけて虫たちが元気になる頃か。さて、日本語には・虫の居所が悪い・腹の虫が収まらない・虫が好かない・虫酸(虫唾)が走る・虫の知らせ・虫が起きる・虫が収まらない・虫を殺す・虫を起こす・疳の虫・泣き虫・弱虫・本の虫・芸の虫・虫がつく・虫の息・・・・と例を挙げると枚挙にいとまがないぐらいに「虫」のつく言葉が多い。虫は昔から「見た目」などから皆に忌み嫌われていたから、あまり良くない意味の言い回しが出来たのだろう・・・と安易に考えていたが本来は「昆虫」とは違う「虫」の意味。江戸時代の初期ごろから、「三尸(し)九虫」といって、人の体内には九つの虫がいて、それぞれが、病気を起こしたり、心の中の意識や感情を呼び起こすのだと広く信じられていという。医学も大脳生理学も心理学も発達していなかった時代なので、心の変調や自分でも制御できない心や複雑な感情を説明するために虫の存在を考えたようだ。つまり、体内の「虫」は季節に関係なく活動する。体内の虫の活動を適度に抑えつつ春を迎えたいもの。
2016/03/30 23:32
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です