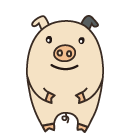小さな国語塾のつぶやき
古文の「」
古文で、よく聞かれる代表的な問いは二つあり、一つは動作主、もう一つは会話文を抜き出すという問題。以前に、同じ動作主の場合は「~て、~て、~て」となると紹介したので今日は会話文について。古文では現代語と違って「」というものがなく改行もされておらず、中学校で習う代表的な見分け方は「文末が『と』で終わる部分までが会話文」」という内容。むろん、それは正しく「と」の後に「言ふ」「曰く」と続くことが多いため分かりやすい。そのため、大半の中学生は会話の終わりは間違いなく抜き出せるのだが・・・・、問題は会話のがどこから始まるか?!内容から考えないといけないのだが・・・・時々「○○言ふには・・・・・・と言ふ」のように「言」が2回書いてあることがある。この場合は超ラッキーで「言ふには」の直後「・・・・・・」が会話文になる。つまり現代語の「」の代わりに「言ふ」という言葉で会話の内容を挟んでいるのである。この形に慣れるまでは「言う」が2回もある!一体どこから会話文?!となるのだが、先にも書いたように「言う」は「」の代わり!と認識して割り切って覚えると正答率がアップし、しかも楽しくなる。昔の人の気分になってぜひ古文の決まり事を覚えてみると世界が広がること間違いなし。
2016/03/29 17:49
-

-
コメントするには会員登録後、ログインが必要です